 東京・春・音楽祭2025「パルジファル」(演奏会形式)
東京・春・音楽祭2025「パルジファル」(演奏会形式)
〇2025年3月27日(木)15:00〜19:55
〇東京文化会館
〇3階R4列4番(3階上手側バルコニー最後列中央寄り)
〇パルジファル=ステュアート・スケルトン(T)、クンドリ=ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー(MS)、アムフォルタス=クリスティアン・ゲルハーヘル(Br)、グルネマンツ=タレク・ナズミ(B)、クリングゾル=シム・インスン(Br)、ティトゥレル=水島正樹(B)他
〇マレク・ヤノフスキ指揮N響(16-14-12-10-8、下手より1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)(コンマス=郷古、第2V=森田、Va=佐々木、Vc=藤森、Cb=市川、Fl=神田、Ob=??村、Cl=松本、Fg=水谷、Hr=今井、Tp=菊本、Tb=新田、Tu=池田、Timp=植松)、東京オペラシンガーズ(24-56)

ゲルハーヘルの嘆きにボロ泣き
上野の春の文化イベントとしてすっかり定着した感のある東京・春・音楽祭だが、私にとってはこれまでほとんど無縁のものだった。年度の変わり目で公私にわたりそれどころではなかったからである。今もその状況にあまり変わりはないのだが、少しは融通が利くようになったので、これはという公演は多少無理して行くことにした。
ヤノフスキ指揮による「パルジファル」は元々2021年に予定されていたがコロナの影響で中止となり、今回ようやくリベンジを果たした形だ。主要な配役はゲルハーヘル以外変わっているが、やはりヤノフスキが振るとあっては行かないわけにはいかない。9割以上の入り。3月末の平日の午後3時に始まる公演なんかに誰が行けるんや?と今までは思っていたが、晴れて?その一員になれただけでも嬉しい。
前奏曲、冒頭から音楽の流れが心地良い。その一方で、聖餐のモチーフの頂点となる3小節目のGはfだが、2回目の頂点となる22のHはsf。両者を明確に区別。
第1幕、グルネマンツは上手、クンドリ、アムフォルタス、パルジファルは下手に登場。
場面転換の音楽が始まるとパルジファルとグルネマンツは一旦退場。男声のみ舞台後方の合唱席へ。頂点に達したところでドラムのトレモロが入る。演奏会形式でないと気付かない。グロッケンシュピールは舞台裏から録音?を流しているようだ。グルネマンツが再び上手に登場するが、一緒に連れてきたはずのパルジファルは出てこない。信仰のモチーフを歌う女声と男声の一部は1階席後方から歌っているようだ。
第2幕、クリングゾルは上手に登場するが、指揮者近くでなく袖寄りに立つので、私の席からは頭がチラチラ見える程度。クンドリは下手、パルジファルは上手に登場。花の乙女たちのうちソリストは舞台両端に設けられた低い山台の上に3人ずつ立ち、合唱(女声)は合唱席から歌う。
最後のティンパニのトレモロが鳴り終わらないうちに拍手のフライング約1名。
第3幕、グルネマンツは上手、クンドリとパルジファルは下手。クンドリは歌い終わった後も場面転換の音楽が始まるまで退場せず座っている。パルジファルが自分を責める歌を歌った後グルネマンツが"Nicht so."と歌う場面があり、字幕では「そんなことはありません」と表示されていたが、このセリフはパルジファルを介抱しようとするクンドリに対してのものであり、その後にパルジファルの身体を洗って清めるよう指示するので、通常は「そうではない」と訳されるはず。字幕担当の広瀬大介さんに意図を確かめてみたい。
場面転換の音楽の間に男声が合唱席へ。第1幕と異なりこの場では全員登場。下手にアムフォルタス。彼を救いに来るパルジファルは上手に登場。
最後の和音が鳴り終わり、聴衆が余韻に浸り、指揮者がまだ頭を下げていない状況で拍手のフライング約1名。
全幕を通して、場面に応じてホリゾントの下からの照明の色が変わる。
スケルトンは張りのある声で正にヘルデンテナーという感じだが、やや安定感に欠ける。バウムガルトナーは硬質な声で、もう少し響きに広がりが欲しいところ。ほとんど楽譜に目を落としながら歌っているせいもあるかも。せめて第3幕くらいは暗譜で歌ってほしい。ナズミはグルネマンツにしては若々しい声だが、よく響き、堂々たる歌いぶり。シムもやや明るめの声で楽天的な悪役ぶりで存在感を示す。
しかし、何と言っても圧倒されたのはゲルハーヘルのアムフォルタス。明るい声質なのだが、それゆえにアムフォルタスの悩み、苦しみがストレートに聴く者に伝わってくる。歌いぶりもドラマチックで、それでいて誠実さにあふれ、芝居臭い感じが全くない。特に第1幕の嘆きの歌は出色の出来。この場面でボロボロ泣いたのは初めて。第3幕のソロにも聴き惚れる。
脇を固める日本人歌手たちも手堅い歌いぶり。
東京オペラシンガーズの合唱は、パワーよりハーモニー重視で、見事に整った歌いぶり。バイロイト祝祭合唱団指揮者のエベルハルト・フリードリヒが加わった影響もあるだろう。
ヤノフスキのワーグナーは昔からテンポが速いのはわかっていたが、今回はホワイエに表示されていた予定上演時間よりも短いのにびっくり。第1幕約95分、第2幕約58分、第3幕約63分。40年近く前にFMで聴いたフランス放送管のライブよりも速いのではないか?テンポ自体と言うより、グラン・パウゼが短かったり、他の指揮者ならフレーズが一段落するところで一呼吸置くのを続けて弾かせたりするのが影響しているのではないか?
ただ驚くのは、そのようなフレーズ感覚なのに、全くせわしない感じがしないどころか、宇宙のような広がりと深遠な雰囲気が終始保たれていること。彼にしか創れない音楽空間と言っていいだろう。
N響も低弦が節目節目で充実した響きを聴かせ、その堅固な土台の上に壮大な音楽の伽藍を創り上げる。管楽器、特にEHr(池田)やBCl(山根)が随所で歌手たちに絡むのがきちんと聴こえるのも、演奏会形式の醍醐味。
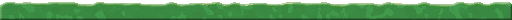
表紙に戻る