 新国立劇場「ウィリアム・テル」(5回公演の3回目)
新国立劇場「ウィリアム・テル」(5回公演の3回目)
〇2024年11月26日(火)14:00〜18:45
〇オペラパレス
〇4階3列32番(4階最後列から2列目ほぼ中央)
〇ギョーム(ウィリアム)・テル=ゲジム・ミシュケタ(Br)、アルノルド・メルクタール=ルネ・バルベラ(T)、マティルド=オルガ・ペレチャッコ(S)、ジェミ=安井陽子(S)、ジェスレル=妻屋秀和(B)、エドヴィージュ=齊藤純子(MS)、メルクタール=田中大輝(BBr)、ヴァルテル=須藤慎吾(Br)他
〇大野和士指揮東フィル(12-10-8-7-5)、新国立競技場合唱団(26-33)
〇ヤニス・コッコス演出

ロッシーニの悪戦苦闘を体感
新国立劇場2024〜25年シーズンで大野和士芸術監督が自ら指揮する演目として取り上げたのは、ロッシーニ最後のオペラ「ウィリアム・テル」。原語(フランス語)による舞台上演としては日本初となる。ウィリアム・テルの物語自体は我が国でも有名だが、ロッシーニのオペラとなると、序曲こそ頻繁に演奏されるものの、全幕上演となると長大だし歌手の確保も大変だし、なかなかハードルが高かったことは想像に難くない。まずは上演までこぎつけた関係者の労を多としたい。ほぼ満席の入り。
序曲における嵐の音楽で紗幕越しに舞台が見える。下手後方から中央に向けて伸びる広い坂を中心に、平らな床面と小さな高台とが組み合わされ、周囲を枝のない木の幹が囲んでいる。スイスの村人たちが立っているところへ天井から数本の巨大な矢が降りてくる。
第1幕、農民の合唱。仕事を終え、結婚式の準備のため一同退場するが、テル家の3人(ウィリアム、エドヴィージュ、ジェミ)とメルクタール家の2人(メルクタールとアルノルド)が残る。メルクタールは息子が結婚しないのを嘆くが、アルノルドは上手手前端で頑なな態度を崩さない。ウィリアムとアルノルドのみ舞台に残り、二重唱。歌い終わるとアルノルド退場。
農民たちが再び集まってくる。結婚する3組の男女はダンサー。メルクタールから花嫁は頭に花冠を授けられる。上手後方の太い枯木から左右に伸びる電飾に灯りがともる。祝福する合唱とともに新郎新婦たちはダンスを披露。そこへ白のドレッドヘアー、白仮面に白装束の謎の人物が奥から現れる。牛や羊などの角と白仮面を付けた男たちとともに踊り、場を盛り上げる。
坂の上方に大きな的が用意される。手前からジェミが矢を放つと見事中心に命中。農民たちが喝采。
得意満面のジェミは枯木に立てかけられた脚立に上って遠くを眺めると、ルートルドが逃げてくるのを農民たちに知らせる。下手奥からルートルド登場、娘をさらおうとしたジェスレルの部下を殺したという。着ている白いシャツに赤い血が付いている。彼を逃がすため、テルは彼を連れて上手へ退場。
最奥が明るくなると黒兜の兵士たちが横1列に並ぶ。その奥にサーチライトがたくさん並んでいる。ジェスレルの部下ロドルフは赤い帯の入った軍隊帽に軍服姿。ルートルドを捜索するため農民たちを威嚇。天井からサーチライトが彼らを照らす。
ロドルフがルートルドを逃がした者の名を言うよう告げると、メルクタールは「この村に密告者はいない」と答える。メルクタールは兵士たちに連行される。
第2幕、第1幕とほぼ同じ舞台だが、天井から矢が何本も降りた状態。舞台裏で狩人の合唱が歌われる中、下手奥からアルノルド、上手奥からマティルド登場。アルノルドを追うが見失う。
マティルドのロマンスの後、後方からアルノルド現れ、2人は抱き合う。上手手前に三角形の台があり、そこを中心に二重唱。歌い終わるとマティルドは脱いだ赤いマントを残したまま上手へ退場。
入れ違いに坂の上からテルとヴァルテル登場。懐中電灯を手にしている。アルノルドとマティルドの関係を知ったテルは、懐中電灯をマントに充てて彼を非難。さらにヴァルテルから父の死を告げられ、父が羽織っていた赤いマフラーを投げられる。アルノルドは仇を討ち独立のために戦うことを誓う。
三州の男たちが下手の坂、奥、手前から順に集まってくる。全員で気勢を上げる合唱で幕。
第3幕、アルトドルフ宮殿の庭の礼拝堂。上手後方から手前だけが通路のように明るく照らされ、第2幕まで枯木だったものが塔のようなしつらえになり、てっぺんから矢先が突き出している。
アルノルドから別れを告げられたマティルドによる絶望のアリア。歌い終わると2人は別々に退場。
舞台全体が明るくなり、広場の場面に。下手から民衆が現れ、最奥から兵士たちに追い立てられるように手前へ移動。下手手前に階段付きの高台が置かれる。上手から登場したジェスレルは赤い帯付きの帽子に軍服姿。帽子をトロフィーの代わりに竿の先に付け、部下に竿を回させて民衆に跪くよう命じる。兵士たちは民衆を4列に強制的に整列させる。
ジェスレルは高台の上から、民衆の合唱や踊りを見物。第1幕で白装束の人物を演じたダンサーが今度はパイナップル風の髪型で登場。軍服姿の男3人とキャバレー風衣装の女によるダンスを披露させるほか、第1幕で結婚した新郎新婦たちを連れてきて新婦だけ引き離し、花冠を取ってトナカイの角を被せ、軍服男たちと無理やりデュエットさせるなどしていたぶる。
テルとジェミが頭を下げないのを見咎めたジェスレル、ロドルフも加わっての四重唱。息子の頭にリンゴを載せて射落とすよう命ぜられたテル、一時は絶望して膝を屈するも息子に励まされてアリア「動いてはいけない」を歌う。
ジェミは塔の下に立ち、頭にリンゴを載せられる。テルが中央手前から矢を放つと、塔の中から矢が飛び出してリンゴは真っ二つになって落ちる。喝采を浴びるテルだが、もう1本矢を持っていたことをジェスレルに見咎められ、ジェミとともに逮捕される。今にもジェスレルに襲い掛かろうとする民衆を兵士たちが必死に止めている。そこへマティルドが割って入ってジェミを助け下手手前でかくまうが、テルは兵士たちに連行され、上手へ退場。
第4幕、矢の形にくり抜かれた壁が舞台前方に立てかけられる。その手前がメルクタールの家という設定。中央手前にジャケットのかかった椅子。奥からアルノルドが現れ、家の中に入り、赤いマフラーを椅子に掛けてアリアを歌う。兵士たちに外から呼ばれると、彼らを率いて奥へ退場。
入れ違いに舞台手前に女たち登場。ルツェルン湖畔の岩場という設定。夫と息子が死んだと思い込んでいるエドヴィージュを女性たちが励ます。上手奥から声がして、ジェミが走って戻ってくる。続いてマティルドも登場。三重唱となる。
壁が上がって舞台奥まで見えるようになる。上手手前にテルが現れ、坂の途中にいるエドヴィージュとジェミに、火のことを尋ねる。下手後方が燃えている。ジェミはのろし代わりに家を燃やしたのだという。奥からジェスレルと兵士たちが現れる。テルがジェスレルに向かって矢を放つと、ジェスレルは左手で覆っていたコートを開く。すると矢が胸に刺さっている。苦しみながら手前までよろけてきて倒れる。彼が倒れた部分だけ舞台がせり下がる。一同集まってきて、独立を祝う合唱。マティルドだけは彼らを見守りながら一人寂しく下手の坂を上ってゆく。
ミシュケタはアルバニア出身。芯のしっかりした声で独立の英雄にふさわしい歌いぶり。バルベラは米国出身。頻繁に登場するハイCを難なく響かせ、こちらも出色の出来。ペレチャッコはロシア出身だがリリックな声質で、オーストリア皇女にぴったりの気品が備わっている。
日本人歌手たちも彼らと対等に渡り合う。安井は演技では少年らしく転んだときに足を大袈裟に振るなどの茶目っ気を見せる一方で、歌では貫通力のある声を存分に響かせる。齊藤も存在感十分の声で、特に第4幕ソロと三重唱では情感のこもった表現力が抜群。妻屋がいつもに比べてすこし声の響きが薄かったのが残念。須藤と田中は安定した歌いぶり。
大野指揮の東フィルは前半でやや中音域の貧しい部分もあったが、後半は充実した響き。合唱もいつもながら安定したハーモニーだが、第3幕の無理矢理歌わされる場面は少し立派過ぎたかも。
コッコスの演出はシンプルな舞台を各場面にうまく当てはめていた一方、第1幕ではどこを見ていいのかわからなくなるような場面もあり、人物たちの動きが整理しきれていない感じ。
肝心のロッシーニの音楽だが、当時フランスで流行りつつあったグランド・オペラの形式にいかに自身の音楽を活かすか、悪戦苦闘している感じが伝わってくる。「セミラーミデ」「湖上の美人」などのセリアでは長時間でも全く飽きないのに、第1幕のダンス音楽など正直退屈に聴こえる場面もしばしば。その一方で第2幕終盤のロッシーニ・クレッシェンドや第4幕最後の合唱などロッシーニらしさが存分に発揮される場面もあるし、重唱の多彩さはベッリーニ、ドニゼッティやヴェルディにも受け継がれる起点とも言うべき充実ぶり。やはりロッシーニはイタリア・オペラの歴史の中で正当に評価されるべきなのだと思う。
あと初めて全編を生で聴いて気付いたのだが、あの有名な序曲に登場する主題は本編の中では全く使われていないのである。同様の例はモーツァルト「フィガロの結婚」くらいしか思い付かない。このあたりにもロッシーニがこのオペラを作曲するにあたっていかに苦労したか、垣間見えるような気がする。
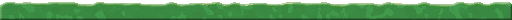
表紙に戻る