 長島剛子・梅本実 リートデュオ・リサイタル
長島剛子・梅本実 リートデュオ・リサイタル
〇2024年10月22日(火)19:00〜20:50
〇東京文化会館小ホール
〇シェーンベルク「7つの初期の歌曲」より「私の心は深い空洞のようだ」「少女の歌」「男の気がかり」「私を慰めるお前の眼差し」、同「4つの歌曲」Op2、同「キャバレー・ソング」より「ガラテーア」「分をわきまえた愛人」「ギガルレッテ」
同「月に憑かれたピエロ」Op21(Fl、ピッコロ=高橋聖純(「たか」ははしごだか)、Cl,BCl=菊池秀夫、V、Va=漆原啓子、Vc=藤森亮一
+同/川島「ギガルレッテ」、ジーツィンスキー/川島?「ウィーンわが夢の街」

一段上の高みへ
「世紀末から20世紀へ」と題し、その時期のドイツ歌曲を数々披露してきたソプラノの長島剛子、ピアノの梅本実のデュオだが、シェーンベルクの生誕150年にあたる今年は、オール・シェーンベルクのプログラムを組む。しかも彼の代表作である「月に憑かれたピエロ」を取り上げるとあっては、否が応にも期待が高まろうというもの。9割以上の入り、このシリーズで最多の入りかも。
またこのシリーズで初めて、舞台上方に字幕が表示される。これまでプログラムに歌詞対訳が印刷されていたが、本番中の暗い客席では追い切れず、演奏の理解に苦労することも多かっただけに、大変ありがたい。
前半はシェーンベルク初期の歌曲を集める。以前のシリーズで演奏されたものもある。全て調性音楽。
まずは「7つの初期の歌曲」からの4曲。「私の心は深い空洞のようだ」は、アリ地獄へ落ちていくような不気味な内容。「少女の歌」は男の誘いを安易に受け入れる無垢な少女に誰かが人生の警句を告げる。「男の気がかり」はデーメル、「私を慰めるお前の眼差し」はゲーテの詩による。どの曲も梅本の滑らかなタッチとレガート重視のピアノで、長島も歌いやすそう。
「4つの歌曲」の最初の3曲もデーメルの詩。「期待」は池のほとりの屋敷から女の手が差し招いてくるという幻想的な内容だが、変ホ長調でありながらBにほとんど?がついてHになるなど、シェーンベルクがどうやって調性を崩すか、苦心惨憺している感じが伝わる。「君の金色の櫛を僕におくれ」はイエスが娼婦マグダレーネに物乞いするという大胆な内容。最後の"Magdalena"の半音進行を聴くと背筋が寒くなる。「高揚」はタイトル通り情熱が徐々に高まって最後に爆発。しかし後奏のピアノがすぐにその気持を鎮めてゆく。「森の日差し」はヨハネス・シュラーフの詩。春の光が森できらめく様子が途中の3連符を多用したフレーズで表現される。
「キャバレー・ソング」は二人がシェーンベルクの知られざる一面としてわが国に知らしめただけでなく、もはや最も得意なレパートリーの一つになっていると言っても過言ではないだろう。これまで歌われた、格調高いがやや難解な部分もある歌曲と全く異なり、人間の本能のままに愛の喜びを求める心がストレートに音楽として表現されており、3曲とも肩の力が抜けた、陽気で溌剌とした演奏。
後半はいよいよ「月に憑かれたピエロ」。ピアノが舞台後方に下げられ、中央前方に歌手の立つ台が置かれ、その間に下手から高橋、菊池、漆原、藤森の順に席が設けられる。録音用のマイクのセッティングも複雑そうで、休憩時間が終わってもしばらく作業が続く。
まず指揮の川島と奏者たちが登場。全員上下とも黒の衣裳で、梅本も前半の燕尾服姿から着替える。長島も前半のカラフルな衣裳から黒を基調としたドレスに黒のマントを羽織って登場。
第1部、詩人が歌う「月に酔い」「コロンビーヌ」は静かな雰囲気だが、「伊達男」のClの唐突な上昇音階がホールの空気を切り裂く。歌手もこれに続く。「蒼ざめた洗濯女」で音楽は不気味な雰囲気に転じ、「ショパンのワルツ」ではそこに憂鬱さが加わる(題名のワルツがショパンのどの作品かは不明らしいが、最後にピアノが奏でるAis(=B)の連打は第1番の「華麗な大ワルツ」を連想させる)。「聖母」は聖歌のパロディのような音楽、後奏のVcの激しいフレーズとピアノの不協和音の強打が胸に響く。「病める月」はFlと歌手のみによる、闇に吸い込まれていくような音楽。
第2部、「夜」はピアノが低音域で提示するE−G−Esの3音のテーマが他の楽器に受け渡されてゆく。大きな蝶々たちがしだいに太陽を覆い隠していくさまが目に見える。「ピエロへの祈り」、笑いを乞う歌にピアノとClのみが寄り添う。「盗み」では16分音符、32分音符の連打が緊迫感を高める。「赤いミサ」で目を背けたくなるような光景が繰り広げられた後間髪入れず「絞首台の歌」が始まったと思う間もなくピッコロの光が天に突き抜ける。「打ち首」では三日月の刀がピエロの首に迫る有り様が臨場感たっぷりに演奏されるが、後半の器楽のみの音楽で「病める月」が回帰し、聴く者の恐怖をしばし鎮める。「十字架」で再び音楽は激しさと緊迫感を増す。
第3部、「郷愁」でピエロは正気を取り戻すが、聴く者も日常へ戻りたい思いがわいてくる。ただ、それも束の間、「悪趣味」「パロディ」では再び暴力的で退廃的な音楽が続く。「月のしみ」ではピエロの焦りが聴く者を不安に陥れる。「セレナード」はピエロとカッサンドラの最終決戦。それがようやく収まると詩人は「帰郷」の舟歌に乗って故郷のベルガモに帰り、「おお なつかしい香り」を歌うが、最後の"Marchenzait!"(なつかしい!)の沈むような音型を聴いても、とても幸福な気分になれない。
長島は歌唱用の声を少し多めに取り入れつつ地声と巧みに使い分け、この曲の不思議で屈折した世界を見事に表現。梅本のピアノはシェーンベルクでありながら古典的な響きに聴こえることもしばしば。元札響首席奏者の高橋、アンサンブル・ノマドのメンバーの菊池、N響主席の藤森の研ぎ澄まされた演奏ぶりも素晴らしい。嬉しかったのは、30年以上ぶりに生で聴いた漆原のヴァイオリン。技術は言うまでもないが若い頃の瑞々しい響きも全く変わらず、"Marchenzait!"と高らかに叫びたい気持を抑える。
彼らだけでアンサンブルとして既に完成形なのだが、今回はそこに作曲家で現代音楽のスペシャリストとして川島が指揮したことで、ジグソーパズルの最後のピースをはめたような達成感が伝わるとともに、この難曲が格段に身近なものとなったのは大きい。彼が振ってくれなければ、何回聴いても「ショパンのワルツ」が3拍子で「帰郷」が8分の6拍子だとはわからないだろう。
出演者全員国立音大にポストを有し、その面から見れば梅本学長をリーダーとする「国立ヴィルトゥオーゾ」と呼びたくなる。
アンコールでは「ギガルレッテ」を川島の編曲で演奏し、さらに「ウィーンわが夢の街」も同じ編成で披露(おそらくこれも川島の編曲だろう、字幕にはウィーンの街の風景が映される)という、何とも贅沢なデザート付。「世紀末から20世紀へ」シリーズが一つの集大成を迎えるだけでなく、さらに一段高みへと昇っていったことを実感。
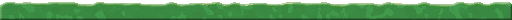
表紙に戻る