 ヴァイグレ指揮読響
ヴァイグレ指揮読響
○2024年10月9日(水)19:00〜21:25
○サントリーホール
○2階C5列33番(2階5列目やや上手寄り)
○伊福部昭 舞踊曲「サロメ」より「7つのヴェールの踊り」
ブラームス「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」Op77(約35分)(14-12-10-8-6)
+バッハ「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番ハ長調」BWV1005より「ラルゴ」(以上V=クリスティアン・テツラフ)
ラフマニノフ「交響曲第2番ホ短調」Op27(約56分)
〇ヴァイグレ指揮読響(16-14-12-10-8)(コンマス=日下)

シュトラウス風ラフマニノフ
先月から今月にかけて読響常任指揮者のヴァイグレが3つのプログラムを振るというのに、なかなか日程の調整がつかず、辛うじて3つ目のプログラムに滑り込む。チケットは完売、ほぼ満席の入り。
1曲目は彼にしては珍しく伊福部昭の曲。1948年に初演されたバレエ用の音楽を、作曲者自身が1987年に演奏会用に改編したもの。
アルトフルートの怪しげな下降音階から始まり、ハープが応える。そのメロディが他の楽器に受け継がれてゆく。続いてゴジラの行進風のリズムを弦が刻みながら次の舞曲へ。管楽器がメロディを主導し、徐々に熱がこもってくる。その後弦が民謡風だが上下にうねるようなメロディを提示しながら盛り上げる。その熱狂が一旦鎮まった後、弦が再び野性的なリズムを刻み、管が騒ぎ、打楽器があおる。ヴァイグレにしては珍しく縦の線を揃えるのを重視するような振り方。
ブラームスのヴァイオリン協奏曲のソリストにはテツラフが登場。生で聴くのは1990年代前半にドホナーニ指揮クリーヴランド管弦楽団の来日公演でシェーンベルクの協奏曲を聴いて以来。早いもので彼ももう60近いのか。
第1楽章、ほぼ標準的なテンポ。オケが第2主題を提示する80〜81小節にかけての8分音符+16分休符+16分音符のリズムを鋭く刻ませるあたり、いかにもヴァイグレらしい。
90からソロが一気に2オクターブ以上を駆け上がる。少しテンポを上げる。164以降の重音のキレが抜群。204以降では一転してすっきりと歌い上げる。246以降の第2主題の刻み方はヴァイグレ同様鋭い。そこから一気に頂点へ。
ハ短調に転じてソロが弱音で歌う312以降、細心の注意を払いながら進み、オケが休符に入る330〜331では消え入るような感じに。332からfでトリルの連続で昇っていくが、今一つ迫力に欠ける。ただ、続く337〜339の高速アルペジオは見事。348以降大きな跳躍を繰り返しながら上下するフレーズも息つく暇なく進んで第2の頂点へ。
カデンツァも速いテンポでどんどん弾いていく一方で、ささやくような弱音も織り交ぜ、硬軟巧みに使い分ける。
第2楽章、ほぼ標準的テンポ。Obソロが心地良い。その心地良さをソロも引き継ぎ、やや落ち着いたフレージング。しかし、嬰ヘ短調に転じる52以降、再び研ぎ澄まされた弾きぶりとなり、63のフェルマータ以降の弱音もすすり泣くような歌いぶりに。それが75に至ってヘ長調に戻り、ほっと一息。
第3楽章、速めのテンポ。16分音符3つのフレーズと次の4分音符とを一括りにしたような独特のフレージング。17以降の重音の連続も何の苦もなく弾き進んでゆく。57以降もスピード重視の比較的あっさりしたフレージング。
後半オケが頂点に達した後の222以降で少し落ち着くが、緊張感は保たれたまま。そのままコーダへ突入し、あとは最後まで一気に弾き通す。
カーテンコールではOb首席を2回も立たせる。
彼はこの曲を2度録音しているが、1回目より2回目の方がテンポが速くなっており、この日はさらに速い。ほとんど限界に近い感じ。そのテンポを前提に、細い糸のような音の線に鋭さと繊細さを織り交ぜながら、彼独自の音世界を創り上げる。お気に入りのペーター・グライナー製作の楽器はそんな彼のスタイルに合っているのだろうが、もう少し低音が響いてほしいような気もする。
アンコールは聴衆の興奮を鎮めるような、バッハのラルゴ。
ラフ2の第1楽章、ほぼ標準的テンポ。冒頭の低弦のメロディを丁寧に歌わせる。序奏からラフマニノフらしい行ったり来たりのメロディが重なり、徐々に盛り上がっていくが、着実に響きを積み重ねてゆく。
アレグロ・モデラートに入ってからも同様のアプローチが継続、安心して音楽に身を委ねる。
しかし、通常低弦だけで演奏される最後の音にティンパニを加える。
第2楽章、Hrの主題は力強いが端正なフレージング。モデラートに入ってロマンティックな曲想に転じてからスケルツォ主題の回帰へ徐々に向かっていくところも心地良い。
トリオに入るとせわしない雰囲気に。そこからまた少しずつスケルツォ主題へ戻っていくプロセスも楽しい。
第3楽章、Vaのふくよかなフレーズに乗って1Vが夢見るような主題を提示。6小節目以降のClソロ(金子)に聴き惚れる。
前半の頂点を迎えて音楽が一旦鎮まった後のGPがブルックナー休止を思い起こさせる。その後のHrソロからコンマス→EHr→Flと第1主題が受け継がれていくところも美しい。
第4楽章、3連符のリズムに乗りながら賑やかに進む第1主題。それがひと段落すると、弦がラフマニノフらしく歌う第2主題を提示するが、そこに重なる管楽器の和音には2拍3連符が延々と続く。それも落ち着いたところでアダージョとなり、1Vが第3楽章の主題の回想をするところも何だか懐かしい。
その後低弦から始まる下降音階を様々なパートが受け継ぎながら息長く盛り上げて第1主題に回帰するあたりの音楽の運びも素晴らしい。
終盤のピウ・モッソでもほとんどテンポは変えず、端正さを保ったまま曲を締めくくる。拍手のフライング若干名。
ラフマニノフ特有の上下を行き来するメロディが、ヴァイグレの手にかかるとR.シュトラウス風の色気を帯びてくるのが実に面白い。また、オケ全体の響きが盛り上がっていく中で、控え目ながらも着実に低弦(特にCb)の存在感を高めていくあたりも彼らしい。
楽員解散後ヴァイグレの一般参賀。
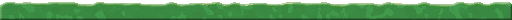
表紙に戻る