 ヴァイグレ指揮読響
ヴァイグレ指揮読響
〇2024年4月26日(金)19:00〜20:45
〇サントリーホール
〇2階RA6列8番(2階ステージ上手側バルコニー最後列)
〇ブラームス「大学祝典序曲」Op80(14-12-10-8-6)
コルンゴルト「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」Op35(約23分)+エネスク「ルーマニアの様式による歌」(以上V=ロザンネ・フィリッペンス)(12-10-8-6-4)
ベートーヴェン「交響曲第4番変ロ長調」Op60(約33分、第1,3,4楽章繰り返し実施)
(14-12-10-8-6、下手から1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)(コンマス=林)

大学祝典交響曲
読響常任指揮者ヴァイグレは、今月東京・春・音楽祭で演奏会形式の「エレクトラ」を熱演し、この日は得意のドイツ物を並べる。同じプログラムが明後日横浜みなとみらいホールでも演奏される。7割程度の入り。
「大学祝典序曲」は、今まで聴いた演奏で特に印象に残っているものはない。正直いつもの「オケのウォーミングアップ曲」のようなつもりでこちらもいたのだが、冒頭の1Vの装飾音からはっきり聴かせるので、思わず身を乗り出す。緊張感に満ちた序奏に続き、63小節以降Tpによる「われらが立派な校舎を建てた」のメロディが提示され、そこから88以降の全奏まで盛り上げていくまでの音楽のスケール感が素晴らしい。128以降1Vと2Vが分担して提示する「祖国の父」のメロディの流れも心地良い。156以降Fgが提示する「新入生の歌」のメロディで一段と雰囲気が明るくなるが、230以降再度提示された後241以降短調に転じて不穏な雰囲気に。まるで新入生たちをカルト集団が惹き込もうとするかのようだ。しかし、それも290以降ハ長調に転じて再び祝祭的な雰囲気に戻る。そして379以降最後の「ガウデアムス」(さあ、愉快にやろう)が華々しく提示され、大団円に。この間交響曲の1つの楽章と同じくらい、曲想によってわずかにテンポを揺らしたり、メロディパートと伴奏パートを絡ませたりする。この曲をここまで豊かで重層的な音楽に創り上げるのも、ヴァイグレにしかできない芸当である。
コルンゴルトのヴァイオリン協奏曲は近年演奏機会に恵まれるようになってきた。私もようやく生で聴くことができる。フィリッペンスはオランダ出身、欧州ではそろそろ中堅といったあたりの位置付けか。紺地に花柄のワンピース姿。
第1楽章、速めのテンポでコルンゴルト特有のロマンティックなメロディを伸びやかに歌わせる。高音のトリルを響かせてメロディをオケにバトンタッチすると、ソロも伴奏的に絡んでゆく。重音が続くカデンツァもためらうことなくどんどん弾き進んでゆき、再び高音のトリルで冒頭メロディへ。コーダの速いパッセージも難なく弾き進み、軽やかさすら感じる。
第2楽章、ヴァイオリン協奏曲には珍しいHp、チェレスタ、ヴィボラフォンが奏でる幻想的なハーモニーの上を、ソロが平易なメロディを提示。美しいが、歌わせ方は少し淡白。
第3楽章、速めのテンポで舞曲風のメロディを軽快に弾いてゆく。それを端折ったような主題でオケが応える。ロマの踊りを連想させるような、エネルギッシュな音楽。終盤にはHrが主題を先導して盛り上げる。
どの曲もコルンゴルト自身の映画音楽が使われ、初演時には「ハリウッド協奏曲」と揶揄されたそうだ。確かに親しみやすいメロディが目立つ一方で、半音進行をスパイス的に用いるあたりは紛れもなく後期ロマン派の音楽とも言える。そんな音楽をフィリッペンスは爽やかに弾き通したが、コルンゴルト特有の耽美的なハーモニーがやや薄まって聴こえたのが残念。ただ、音楽への真摯なアプローチには好感が持てる。
フィリッペンスはヴァイグレと変わらないくらいの長身で、彼の肩に腕を回せるくらい。
アンコールはエネスコのルーマニア民謡風の曲。ロマたちが歌い踊る姿が目に浮かぶ。
後半は前半の曲で使われた打楽器、Hpなどが片付けられ、シンプルな編成に。
ベト4第1楽章、テンポは標準的だが慎重に一歩ずつ歩んでゆく。39小節以降のアレグロ・ヴィヴァーチェはやや速めだが、突進する感じはない。159以降のppとffの繰り返しもはっきり区別するが、極端な差は付けない。
81以降主題を低弦が提示するのに対し、84のVの5連符の上昇フレーズを強調。
展開部の後半、321以降、それまで硬いバチを使っていたティンパニが、ここから再現部の355に至るまで、この部分だけ柔らかいバチに変える。
終盤489〜490のpのフレーズに応える491の全奏の音量は楽譜通りfで、圧倒する感じはない。
第2楽章、クライバーほどではないが、かなり速いテンポで音楽を先へ先へと進めてゆく。17以降頻繁に登場する弦の分散和音を丁寧に歌わせる。50以降の変ホ短調の下降音階は重厚な響き。
最後の2音は楽譜通り8分音符で、短めに切る。
第3楽章、ほぼ標準的テンポ。主部もトリオもテンポはほとんど変えないが、快活でエネルギーに満ちた主部に対し、トリオでは落ち着いた、ほのぼのとしたハーモニー。
第4楽章もほぼ標準的テンポで、猪突猛進の感じはない。5以降の弦の細かいフレーズをきっちり弾かせ、小さなブロックを隙間なく積み上げていくような感じ。66〜69などのsfも必要以上に強調しない。後半のFgや低弦によるメロディも明瞭に聴こえる。
奇をてらわず、端正にまとめたベートーヴェン。
カーテンコールではまずFg首席の井上を立たせる。
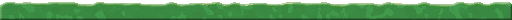
表紙に戻る