 井上道義指揮N響(2回公演の2日目)
井上道義指揮N響(2回公演の2日目)
〇2024年2月4日(日)14:00〜16:10
〇NHKホール
〇3階11列21番(3階最後列から3列目ほぼ中央)
〇ヨハン・シュトラウス2世「クラップフェンの森で」Op336、ショスタコーヴィチ「舞台管弦楽のための組曲第1番」(10-8-6-6-4)
同「交響曲第13番変ロ短調」(バビ・ヤール)(約64分)(B=アレクセイ・ティホミーロフ、オルフェイ・ドレンガル男声合唱団(59))
(16-14-12-10-8、下手から1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)(コンマス=郷古、第2V=大宮、Va=佐々木、Vc=辻本、Cb=吉田、Fl=神田、Ob=吉村、Cl=松本、Fg=水谷、Hr=今井、Tp=菊本、Tb=古賀、Tu=池田、Timp=植松)

ショスタコーヴィチの多面性を見事に表現
今年末での引退を表明している井上道義がN響定期へ最後の登場。得意のショスタコーヴィチを取り上げるとあっては、行かないわけにはいかない。ほぼ満席の入り。
前半は指揮台なし。
最初にヨハン・シュトラウス2世が置かれているのに驚いたが、ポルカ「クラップフェンの森で」は元々彼がペテルブルグへ演奏旅行した際に作曲したものをウィーンの聴衆向けに改題したものだそうで、ロシア所縁の作品と言える。カッコウ笛(竹島悟史)が頻繁に登場するが、指揮者のテンポが殆ど毎回異なるので、G−Eの単純なフレーズが実に多彩に演奏される。終盤では笛を落として聴衆の笑いを誘う場面も。
「舞台管弦楽のための組曲第1番」は、ショスタコーヴィチが1930〜50年代に大衆向けに作曲したバレエや映画音楽から抜粋したもの。楽器編成が面白く、木管はObとFgが1人ずつだが、アルト・サックスとテナー・サックスが2人ずつ加わる。また、指揮者の目の前にアコーディオンとギター奏者も座る。
「行進曲」は金管の技巧的なフレーズが耳に残る。
「リリック・ワルツ」はいかにもロシア風の哀愁漂う音楽で、サックスとアコーディオンが活躍する。
「小さなポルカ」は快活な曲風で、シロフォンからサックスへメロディが受け渡される。
「ワルツ第2番」は映画「アイズ・ワイド・シャット」で使われたらしい。こちらも哀愁に満ちたメロディを前半は弦、後半はTbが奏でる。
どの曲も井上は舞台上を所狭しと動きながら、いつものダイナミックな振りで団員たちを引っ張る。さながら「井上版ニュー・イヤー・コンサート」といったところ。
後半は「バビ・ヤール」。井上はこれまでN響とショスタコーヴィチの交響曲をいくつか取り上げてきたが、声楽付の交響曲は最初で最後となる。
休憩が終わり、合唱団員たちがステージに登場すると自然と拍手が起き、全員揃うと一段と大きな拍手に。前半オケメンバーの登場時にも拍手が起きたが、今日の聴衆はなかなかレベルが高い。
ティホミーロフに続いて登場した井上も、合唱団員たちを立たせて聴衆に拍手を求める。いえ、もう十分しましたから。
第1楽章「バビ・ヤール」、やや遅めのテンポ。グロッケンシュピールのBの音が静かに断続的に響く中、Tpが葬送行進曲風の主題を提示。合唱とバスが交互にユダヤ人迫害の歴史を、抑えた声だが決然とした節回しで歌ってゆく。オケはショスタコ特有の息長い盛り上がりとなだらかな下り坂で歌を支える。最後のフレーズ(「だからこそわたしは、真のロシア人なのだ」)を指揮者はほとんど余韻を残さず切って終わる。
第2楽章「ユーモア」、オケによる重厚なハ長調の和音から始まるが、その安定を乱すようにバスと合唱がユーモアの力を誇示する歌を歌うと、オケも技巧的なフレーズでそれに応え、盛り立ててゆく。
第3楽章「商店で」、貧しさに耐えながらロシアの民衆の生活を支える女性たちを称える歌だが、終始重苦しい雰囲気の中、バスも合唱もどこか弱々しく響く。
切れ目なく第4楽章「恐怖」、暗鬱な低弦の響きの上をTuソロが行き先の定まらないフレーズを提示。密告社会の恐怖を歌ってゆくが、歌い進むうちに聴いている方も何が本当の恐怖なのか、わからなくなってくる。
切れ目なく第5楽章「立身出世」、ようやく曲調が明るく転じ、Flが変ロ長調の牧歌的なテーマを提示。しかし、立身出世の秘訣を皮肉たっぷりに歌うメロディはその牧歌的雰囲気を切り裂きながらフーガ風に重なってゆく。終盤にようやく弦が牧歌的テーマを弦が提示して落ち着くが、その上をチェレスタによる第1楽章の主題とグロッケンシュピールのBの音が静かに響く。
ティホミーロフはふくよかな響きで声質は温かみを感じさせる一方、時折手振りを交えた雄弁な歌いぶり。対するオルフェイ・ドレンガル合唱団はユニゾンによる歌唱だが、全体的に暗めで深い声質。ときにはティホミーロフに寄り添い、ときには突っ込み、反発する。
井上は指揮台の上という制約はありながらも縦横無尽に動き回ってこの曲の魅力を最大限に引き出そうとし、N響も十二分に応える。前半の狂気と攻撃性に満ちた音楽が後半では暗い響きが続いてゆき、最後に一見夢見心地の音楽に到達したかに思えるが、最後の最後で背筋が寒くなる。井上&N響の集大成に相応しい名演。
しかし、井上が本当に伝えたかったのは、前半の組曲と後半の「バビ・ヤール」を組み合わせることで、こんな正反対の性格の曲を同じショスタコーヴィチが作曲したのだ、ということだろう。
カーテンコールでの井上は終始上機嫌、オケの団員やソロ歌手、合唱団員たちを称え、団員が花束を渡そうとしてもじらしてなかなか受け取らない。受け取ると今度は花束を抱いて舞台上で回り出す。一般参賀では横幅の広いNHKホールの上手端まで行って聴衆に応え、途中から腰を曲げて爺さん歩きをするなど、最後までノリノリ。こんな姿が観られるのもあと数回である。
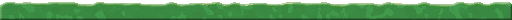
表紙に戻る