 セバスティアン・ヴァイグレ指揮読響
セバスティアン・ヴァイグレ指揮読響
〇2023年10月17日(火)19:00〜21:10
〇サントリーホール
〇2階RA4列16番(2階上手ブロック4列目Pブロック寄り)
〇ヒンデミット「主題と変奏「4つの気質」(8-6-4-3-3)+ゴドフスキ「トリアコンタメロン第11番」(なつかしきウィーン)(P=ルーカス・ゲニューシャス)
アイスラー「ドイツ交響曲」Op50(日本初演)(S=アンナ・ガブラー、MS=クリスタ・マイヤー、Br=ディートリヒ・ヘンシェル、B=ファルク・シュトゥルックマン、新国立劇場合唱団(44-36)、合唱指揮=冨平恭平)(14-12-10-8-6)(コンマス=長原)

誰のためのシンフォニー?
読響には今シーズン初登場となる常任指揮者のヴァイグレだが、日本ではなかなか演奏されないドイツの現代音楽2曲を並べる。7割程度の入り。
ヒンデミット「4つの気質」は主題と4つの変奏からなる、ピアノと弦楽合奏のための作品。「4つの気質」とは、人間の性質を体液のタイプによって4つに分けるという古代ギリシャの思想によるもの。着想自体はモンテカルロ・ロシア・バレエ団の振付家、レオニード・マシーンとの関わりから始まったものの、紆余曲折を経て最終的にはジョージ・バランシン振付による作品として戦後に初演される。ニューヨーク・シティ・バレエを代表するレパートリーの一つであり、バレエで馴染みのある方も多いかもしれない。
冒頭の主題が3部構成になっていて、これが意外と長い。主題より短い変奏もある。弦のみによる静かでゆったりした音楽がピアノで遮られ、目まぐるしい掛け合いに。そしてシチリア風、8分の6拍子の舞曲となる。
第1変奏「憂鬱質」はコンマスとピアノとの少々重苦しいアンサンブルから始まり、せわしない弦楽合奏を経て、行進曲風に。
第2変奏「多血質」は一転して軽快なワルツ。ヴァイグレ得意の左右に腰を揺らす指揮ぶりで。少しウキウキした気分に。
第3変奏「粘液質」は弦楽五重奏、すなわち各パートの首席奏者たちとピアノとのやり取り。再び気分が沈んでくる。
第4変奏「胆汁質」はまた弦楽合奏とピアノとのアンサンブルに戻り、スケールの大きな充実した音楽に。最後はハ長調に解決して堂々たるフィナーレ。
ゲニューシャスはヴァイグレをしのぐ大男だが、ピアノの弾きぶりはロシアン・ピアニズムの正当な継承者と呼ぶにふさわしい。軽いタッチで豊かな響きを創り出し、重厚さと繊細さを兼ね備え、早くも巨匠の風格を漂わせる。ヒンデミットの前衛性よりも、古典的な音楽として正面から向き合い、スコアに書かれた音符を忠実に音にしているように聴こえる。
アンコールのゴドフスキもお洒落な小品で、ピアニストとしての表現の幅広さを披露。
後半はいよいよアイスラー「ドイツ交響曲」の日本初演。アイスラーと言えば東ドイツの作曲家というイメージがあるが、この作品はナチス政権発足前から着想され、アメリカ亡命時代に徐々に書き立たされ、最終的に東ドイツに落ち着いてから完成したという、これまた一筋縄ではいかぬ作品。オケは2管編成だが多くの打楽器、4人の独唱と合唱が加わる。
第1楽章「序曲」、Vaによる不安気なメロディから始まり、徐々に響きが重ねられてゆく。ひと段落したところでPブロックにいる合唱とソプラノが、ドイツに向かって呼び掛ける。終盤にはTpが「インターナショナル」のメロディを提示。ソプラノソロはこの後一旦退場。
第2楽章「強制収容所の闘士たちへ」、低弦がD−Cis−E−Dis(B−A−C−Hを長3度上げた音型)を繰り返す上に調性感のない乾いた音楽が展開。そこにメゾと合唱の歌が加わる。弾圧にめげず共産主義社会を目指す闘士たちへの賛歌だが、突如打ち切られる。
第3楽章「オーケストラのためのエチュード」、文字通り基礎練習のような細かいパッセージが各パートで提示され、発展してゆく。日々の仕事に追われる労働者たちの忙しさを表現しているようにも聴こえる。
間を置かずに第4楽章「回想(ポツダム)」へ。葬送行進曲風のオケにバリトンが戦死者の葬列の様子を歌い、合唱も応える。最後は警官が葬列をデモと見なして鎮圧する壮絶な音楽となる。
第5楽章「ゾンネンブルグにて」、メゾとバリトンがゾンネンブルグ強制収容所の過酷な状況を交互に歌う。途中で"Fuhrer"(総統)という言葉も出てくる。行き場のない、諦めの空気が支配する。
第6楽章「間奏曲」、Va独奏が始まったところで、バスのシュトゥルックマンがフライングで立ちかける。オケのみの演奏だが「深刻な音楽がまだまだ続く」と予告しているようにも聴こえる。
間を置かずに第7楽章「鉛の棺に収められた扇動者の埋葬」へ。バスの静かなソロに続く合唱が"Denn er war ein Hetzer"(なぜなら彼は扇動者だったからだ)をffで絶唱。思わず背筋が寒くなる。続くメゾやバスに応える合唱も、ソロの歌を全否定するかのようなハーモニーで圧倒する。
第8楽章「農民カンタータ」は「凶作」「安全」「嘆きの会話」「農民の歌」の4部構成。前半の2部はバスと合唱のやり取りだが、絶望と神への恨みに満ちた音楽。「嘆きの会話」はハミングの合唱の上に男声団員2人がセリフを交わす。「農民の歌」はバスのソロ。行進曲風で農民に立ち上がるよう呼び掛けるが、半ばやけくその雰囲気も。男声団員6人のセリフが挿入される。
第9楽章「労働者カンタータ」、メゾ、バリトン、合唱が加わる。第二帝国末期から第一次世界大戦、そしてワイマール共和国がナチスに取って代わられるまでのいきさつが、皮肉に満ちた詩を通して歌われる。しばしば挿入される金管のファンファーレ風フレーズが、ドイツの人々を破滅へ煽りたてるように聴こえる。
第10楽章「オーケストラのためのアレグロ」、アイスラーが一度は拒否した十二音技法による、重厚でシンフォニックな音楽。
第11楽章「エピローグ」、前楽章終盤にソプラノが上手からステージ前方に登場、"Seht unsre Sohne"(私たちの息子たちを見て)と訴えかける。"es ist ihnen kalt."(彼らは寒がっているよ)でまたも合唱が絶唱した後、再びソプラノが消え入るような声で"Seht unsre Sohne"を繰り返す。しかし、これに応えるオケもまた消えてゆく。わずか1分程のフィナーレ。
1959年東ドイツで初演されたのだが、反ナチスと労働者階級に寄り添う内容はあるものの、共産主義礼賛の音楽でもなく、聴きようによっては現体制ですら理想のドイツとは程遠い、すなわち東ドイツ政府への批判ともなりかねない。初演時には絶賛されたわけでもないようだが、逆に政府から何のお咎めもなかったのが不思議なくらいだ。
しかし、この曲に込められたテーマは「ドイツ」を別の国や地域に置き換えても十分通用する普遍性を有している。ウクライナやイスラエル、ガザで起きていることについて、私たちはニュースというデータでしか接していないが、この曲を聴くとこれらの国・地域の実情が急に真に迫ってくる。
ソロ歌手たちも全員ヴァイグレとほぼ同じ身長。つまりこの曲を歌うにふさわしい「楽器」を持った歌手たちということ。特にマイヤーは豊かな声量と伸びやかな低音で声のパートを先導し、この曲が表現する世界を創り上げるのに大いに貢献。ガブラーも出番は少ないものの澄み渡った声が耳に残る。ヘンシェルも、時折フィッシャー・ディースカウを思い起こさせる艶やかな響きを織り交ぜながら、雄弁に歌い上げる。シュトゥルックマンは声の力強さは健在だが、歌いぶりはやや危なっかしい。
新国合唱団はいつもながら流石のハーモニー。声量、バランス、ハモリ具合全て言うことなし。そしてヴァイグレ直々の指導もあったようで、ドイツ語の発音も明瞭。
ヴァイグレの指揮ぶりもいつも以上に熱がこもっており、合唱のパートではしばしば口を動かして一緒に歌っている。読響もこれに応え、隙のない演奏。
日本におけるドイツ音楽演奏史に新たなページが加わったことを祝うかのように、ヴァイグレに対していつもより少し長めの一般参賀。
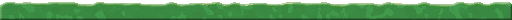
表紙に戻る