 長島剛子・梅本実リートデュオ・リサイタル
長島剛子・梅本実リートデュオ・リサイタル
○2021年10月29日(金)19:00〜20:40
○東京文化会館小ホール
○P列33番(後方から8列目中央)
○ブラームス「スペインの歌」Op6の1、「雨の歌」WoO23、「きみが時折ほほえんでくれさえしたら」Op57の2、「ひばりの囀り」Op70の2、「五月の夜」Op43の2、「セレナーデ」Op106の1
プフィッツナー「まどろみはいよいよ浅く」Op2の6、「捨てられた乙女」Op30の2、「許しを求めて」Op29の1、「だから春の空はそんなに青いの?」Op2の2、「かつては」Op15の4
シェーンベルク「4つの歌曲」Op2(「期待」「君の金色の櫛を僕におくれ」「高揚」「森の日差し」)、ウェーベルン「「第7の環」による5つの歌曲」Op3(「これがあの歌だ」「嵐の中で」「小川の岸辺で」「朝露」「葉の落ちた木が枝を伸ばす」)、ヴァイル「ハッピー・エンド」より「マドロス・タンゴ」「ビルバオ・ソング」、「光の中のベルリン」
+ヘ長調の曲、ブラームス「子守歌」

ドイツ・リートの多様な発展を実感
ソプラノの長島剛子さんとピアノの梅本実さんは、これまでほぼ毎年ドイツリートの歴史と発展を深く掘り下げるリサイタルを開いてきた。前回は2年前だったが私は残念ながら聴けず、次回こそは、と思った昨年はコロナで開かれず。というわけで、私にとってお二人の演奏を聴くのは3年ぶりということになる。
今回は2017年に新しいシリーズとして始めた「ロマン派から20世紀へ」の第3弾、ブラームスからヴァイルまで取り上げるという意欲的なプログラム。半分程度の入り。
ブラームスの「スペインの歌」は、傍らで寝入ってしまった彼を起こそうかと迷う女性の心理が、変ロ短調の細かい分散和音で表現される。「雨の歌」は、ヴァイオリン・ソナタにも転用されたものでなく、その1年前に書かれた作品で、日本でブラームスの自筆譜がある唯一の曲だそうだ。ト短調で雨がポツポツ落ちてくるようなメロディ。「きみが時折ほほえんでくれさえしたら」は、愛の苦悩をピアノが優しく包みこむ。「ひばりの囀り」は、ロ長調のひばりの鳴き声を表すピアノの音型に乗って、訥々と語るようなメロディが歌われる。「五月の夜」は変ホ長調の明るい雰囲気の中で高音で2回繰り返される"Trane"(涙)の下降音型が印象的。「セレナーデ」はチター風のピアノの和音に乗って、陽気で賑やかなメロディが歌われる。
プフィッツナーの「まどろみはいよいよ浅く」は、同じ詩によるブラームスの作品もあるそうだ。嬰ハ短調のさまようようなメロディ。「捨てられた乙女」は嬰ヘ短調のつぶやくようなメロディで始まるが、最後は叫ぶような激しいフレーズで歌い終わる。さらに怒りを鎮めるようなピアノの後奏にもぞくっとする。「許しを求めて」は彼がヘルダーリンの詩に付けた唯一の曲。不穏な不協和音に声が加わると落ち着いた響きに。その後も不安と安心の間を行ったり来たりしながら、最後にようやく平安が訪れる。「だから春の空はそんなに青いの?」はニ長調の素朴な曲風だが、尻切れトンボで終わる。「かつては」はアイヒェンドルフの風刺が効いた詩にレシタティーヴォ風の音楽を付け、幕間劇のようになっている。
シェーンベルク「期待」は4度の和音と半音階の組合せで神秘的な雰囲気に。「君の金色の櫛を僕におくれ」はイエスが娼婦マグダレーナに懇願する歌。最後のマグダレーナを呼びかける下降音型が何とも官能的。「高揚」は感情のほとばしりを一筆書きで表現したような曲。「森の日差し」は最初こそ比較的平易なメロディだがだんだん複雑になり、最後は終始しないで歌が途切れる。
ウェーベルンのOp3の歌曲集はゲオルゲの詩集「第7の環」から抜粋したものだが、作者が美少年を神に崇めるまでの経験を元にしたもの。いずれもウェーベルン特有の、短い中にも凝縮された音楽。ただその中でも3曲目と5曲目は音が比較的多く、ドラマティックな雰囲気もある。
最後はヴァイル。十二音技法から一転して、ポップス風ドイツリートとでも言うべき作品が並ぶ。「マドロス・タンゴ」と「ビルバオ・ソング」は音楽劇「ハッピー・エンド」からのナンバー。前者は酔っぱらった少女の歌。後者はギャングの勇ましい歌。そして、「光の中のベルリン」は1928年に開催された祭典のために書かれた。聴いているとうきうきしてくる。いずれも2017年発売のCDに収録された曲。
ブラームス以降のドイツ・リートが、プフィッツナーのようにまずはロマン派の路線を追求していくものの、そこに限界を感じたシェーンベルクが十二音技法に踏み出してしまい、ウェーベルンがそれを忠実に受け継ぐ一方で、ヴァイルのように違った形の発展を模索する者も出てくる。20世紀以降のドイツ・リートの多様な発展を、声とピアノで実感。
2年ぶりの本番という事情もあってか、長島さんの声は前半時折高音の音程に不安定なところがあったが、後半は徐々に表現が研ぎ澄まされ、ヴァイルではいつもの彼女の溌溂とした歌いぶりが戻っていた。
梅本さんのピアノも終始冴えわたっている。長島さんの声を硬軟自在で支える一方で、シェーンベルクのように長い後奏の曲では、それだけで一つの世界を創り上げる。声より決して出過ぎることがないのに、声に劣らぬ存在感を保ち続けるとは。
アンコール1曲目はヘ長調の軽快な曲。以前このシリーズでも歌われた記憶があるが、思い出せない。
鳴り止まぬ拍手にマイクを持って長島さんだけ登場。コロナの影響で8月くらいまで今回のリサイタルの開催を悩んでいたことや、終演後恒例のロビーでの挨拶は残念ながら行わないとのアナウンス。ここにもコロナに翻弄され、人類にとっての音楽の意義について深く考えた音楽家がいる。
最後のアンコールとして歌われたブラームスの「子守歌」が、コロナに対する子守歌のように聴こえたのは私の空耳か。
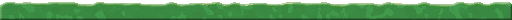
表紙に戻る