 下野竜也指揮新日本フィルハーモニー交響楽団
下野竜也指揮新日本フィルハーモニー交響楽団
○7月2日(木)19:00〜20:55
○サントリーホール
○2階RA6列7番(2階舞台上手側、最後列)
○フィンジ「弦楽オーケストラのための前奏曲」Op25
ヴォーン・ウィリアムズ「テューバ協奏曲ヘ短調」
+同「イングランド民謡による6つの習作」より(Tu=佐藤和彦)
ベートーヴェン「交響曲第6番ヘ長調」Op68(田園)(約44分、第1楽章提示部、第3楽章繰り返し実施)
+バッハ/ストコフスキー「管弦楽組曲第3番」より「アリア」
(12-10-8-6-5、下手から1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)
(コンマス=豊嶋、第2V=ビルマン、Va=篠崎、Vc=川上、Cb=菅沼、Fl=野津、Ob=岡、Cl=重松、Fg=河村、Hr=吉永、Tp=市川、Tb=ガイルス、Timp=川瀬)

リハビリ開始
新型コロナウイルス感染症の影響で長らく中止を余儀なくされてきた演奏会も、ここに来てようやく再開の動きが出始めた。主だったオーケストラやホールのウェブページをあれこれチェックし、何とか新日フィルのチケットを入手。私にとって約5か月ぶりの生演奏である。
会場の雰囲気もコロナ前から一変。入口で1階席と2階席の客の通路が分かれ、2階席の私は右手のエスカレーターの方へ。そこの受付で自分でチケットをもぎって半券を箱に入れ、自分でプログラムを取って2階へ。ホワイエで話す人も少ない。
客席も1席ずつ開けて座る。すなわちほぼ半数の席しか埋まってないのだが、現状ではこれがほぼ「満席」ということになる。
感染予防のためとは言え何とも窮屈な感じがする。今までにない緊張感の中で開演を待つ。
しかし、ホール内の雰囲気は、団員たちがステージへ入場を始めた途端にがらりと変わる。まるでウィーンフィルの来日公演のように、客席から温かい拍手が起こる。日本のオケの普段の定期演奏会ではありえない光景だ。客は全員マスクをしてほとんどしゃべらずじっとしていたけれど、実はみんなこのときを待っていた。おかえりなさい!再開してくれてありがとう!そんなメッセージが拍手を通じて団員たちへ伝えられてゆく。胸が熱くなった。
ステージ上の団員たちは弦楽器も含め、各人に譜面台が割り当てられている。ヴァイオリンやヴィオラの人たちはこれまでより少し間隔を開けて(50センチくらい?)座っている。ただ、マスクをしている人はほとんどいない。管楽器の人たちはいつもと変わらない感じだが、金管奏者の椅子の横には、楽器にたまった唾液を落とすために、布が敷かれている。
コンマスが登場し、チューニングが終わり、いよいよ指揮者登場。第1ヴァイオリンの手前と奥の列の間を通ってくる。右手に白手袋した指揮者とコンマスががっちり握手をする。なかなか考えたねえ。し終わるとすぐに手袋をズボンのポケットにしまうのが可笑しい。
フィンジは20世紀前半に活躍した英国の作曲家。3楽章からなる室内オーケストラの曲として構想されたものの冒頭楽章が、死後に「前奏曲」として出版されたもの。「グリーンスリーブス」を思わせるヘ短調の暗いメロディで始まり、雪解け水を思わせる音楽の流れが心地よい。コンマス、第2ヴァイオリンとチェロの首席の3人によるアンサンブルを経て、最後は天に昇るような輝かしい響きで終わる。早くも心洗われる思い。
ヴォーン・ウィリアムズのテューバ協奏曲は、この楽器が主役になれる貴重な曲。新日本フィル首席の佐藤が指揮台の上手側に座る。白地に黒で模様が描かれたシャツに黒ズボン姿。
第1楽章は打楽器の行進曲風リズムに、ヘ短調の民謡風主題が乗っかっていく。第2楽章は一転してニ長調の牧歌的な音楽。第3楽章は活発で技巧をアピールする場面が多くなる。朗々と響く低音がテューバらしさを強調する一方で、速いパッセージでは楽器が浮き上がりそうに感じるくらいの軽やかさ。
休憩後、再び団員たちがステージへ。あれ、少しメンバーが足りないような?
「田園」第1楽章、ほぼ標準的テンポ。4小節目のフェルマータの前ではテンポを落とさない。13〜14のfと15のpの区別をあまり付けない。やはり弦楽器がいつもより隣と距離が空いているせいか、しっかり合わせようという意識が働いて、フレーズの最後まで弾き切っているように聴こえる。175以降や221以降の低弦もがさがさした感じがなく、輪郭がはっきりしている。
281ではテンポを落とす。終盤440以降も充実した響き。
第2楽章、pやppが多くなっても弦のしっかりしたフレージングは変わらない。ただその分かつてより響きが厚くなり、特に58以降になると、主旋律を奏でる木管がしばしば埋もれかけてしまう。「新しい日常」時代のアンサンブルのコツが求められているように思う。
第2楽章が終わったところで、ティンパニとトランペット奏者が入場。「三密」を可能な限り避ける工夫だろうが、それでもまだ足りないような?
第3楽章、91以降の木管と弦のバランスはいい感じ。133以降のHrがやや不安定。
第4楽章、雨風が本格的になる21に入ってから、ピッコロとトロンボーン奏者が忍び足で入場。これでようやくオールスターキャストに。それにしても、ピッコロはこの楽章の中盤(82以降)から出番があるのだから、第3楽章の前に入場でもよかったのでは?
第5楽章、9以降の1Vのメロディが、一転してかすれ気味の音で始まりハッとする。これが2回目の64以降になるとしっかり芯の通ったメロディラインになり、16分音符の変奏風メロディになる117以降でさらに張り詰めた糸のように響いてゆく。
そして終盤のクライマックスへ向けて、177以降や206以降のVcとFgが、リレー選手の先頭を切るように、豊かな音でつないでゆく。
最後はホール全体を優しく包み込むような響き。
下野にしては奇をてらわず、オーソドックスな解釈だが、団員たちからは音楽を奏でる喜びが自然と湧き上がってくる。
アンコールはバッハの「G線上のアリア」をストコフスキーが編曲した珍しい版。主旋律を1回目はVc、2回目はオリジナル通り1Vが担当する。下野らしい凝った選曲だが、せっかくここまでヘ音を主音とする調の曲で統一していたのに、最後の最後でニ長調の曲になり、画竜点睛を欠く感じがしないでもない。
それでも聴衆はブラヴォーを控える分、いつもより熱のこもった拍手で応える。最後は再び指揮者とコンマスが白手袋を取り出して固い握手。その後下野はその手で顔の汗を拭くご愛嬌も。団員たちが退場した後もしばらく拍手は鳴りやまず、下野と豊嶋が再登場して応える。
行く前は待ちに待った生の音に感激してボロボロ泣くのではないかと予想していたが、実際聴いてみると全く違う感想を抱くこととなった。関係者の努力が結集した、せっかくの演奏会なのに、しかも魂の入った演奏であることが頭ではわかるのに、それを受け止めきれない自分がいる。コロナ以前なら、耳だけでなく全身の毛穴に音楽を感じ取るセンサーが埋め込まれていたはずなのに、この日は多くのセンサーが目覚めないまま終わってしまったような感じ。
少なくとも私の場合、ウィズコロナ時代の音楽文化を守ってゆくには、まず聴衆としてリハビリすることから始めなければならないようだ。
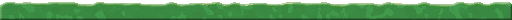
表紙に戻る