 札幌交響楽団東京公演2020
札幌交響楽団東京公演2020
○2月7日(木)19:00〜21:10
○サントリーホール
○2階P6列26番(2階舞台後方、最後列やや下手寄り)
○シューベルト/ウェーベルン「ドイツ舞曲」(12-10-8-6-4)
マーラー「亡き子を偲ぶ歌」(Br=ディートリッヒ・ヘンシェル)(12-10-8-6-5)
ベートーヴェン「交響曲第7番イ長調」Op92(約42分、第1楽章提示部、第3楽章主部、トリオ1回目後半、第4楽章主部、展開部繰り返し実施)(14-12-10-8-7、下手から1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)
+モーツァルト「カッサシオン」K.63より「アンダンテ」

指揮者とオケの幸せな関係
札幌交響楽団はほぼ毎年東京公演を行っているが、昨年は2018年4月に首席指揮者に就任したスイスの指揮者、マティアス・バーメルトとともに東京のファンへお披露目を行った。残念ながらその演奏会に行けなかったので、今回は何としても外すわけにはいかなかった。
1曲目はウェーベルンが管弦楽用に編曲したシューベルトのピアノ曲。バーメルトは若い頃は作曲家としての活動もしており、札響のレパートリーを増やす試みを続けている。以前NHKEテレで放映されたときにはブラームスのピアノ四重奏曲のシェーンベルク編曲版を取り上げていた。この曲も彼のこだわりでプログラムに加えたようだ。
6曲の舞曲が変イ長調と変ロ長調の3曲ずつに分けられ、3曲がひとまとまりで1→2→1→3→1の順に演奏される(後半3曲も同様)。弦と2管の小さな編成だが、気品のある響きで一貫している。
マーラーでCbが1人追加される。
ヘンシェルの陰のある声はこの曲にピッタリ。ただ、やや音程が不安定な場面が気になる。また、短調の曲は非常に雰囲気があっていいのだが、唯一長調の4曲目の"o
sei nicht bang"(不安にとらわれてはならぬ)だけは、もう少しレガートで歌ってほしかった。
真後ろから聴いている分歌手については割り引いて評価しなければならないが、その代わりオケの動きがよくわかって面白い。
ベト7第1楽章、テンポはほぼ標準的。9小節目以降の弦の16分音符を丁寧に刻ませる。48以降ppを維持し、なかなかクレッシェンドしない。
63以降の提示部もほぼ標準的なテンポ。88のフェルマータはほとんど付けずに弦の上昇音型へ。突進でなく軽快に進んでいく。100以降のpと142以降のppの区別を明確に付ける。119,121の1Vと120,122の2V,Vaのフレーズを対比して浮き立たせる。
181以降、弦を中心とする息の長いやり取りではppを忠実に維持し、195以降のクレッシェンドで201のfへ一気に。236以降のVa以下とVが交代しながら盛り上げていく場面も心地良い。
300のフェルマータも短め、直後のObソロが少し乱れる。
終盤の391以降もppをずっと維持。雪の中で春が来るのを待つような感じ。そして423以降の頂点へ。
第2楽章、やや遅めのテンポ。ここでも3以降のpと19以降のppをはっきり区別。ここでもクレッシェンドは抑え目に進めて、ffの全奏になる75以降で全開させる感じ。
イ長調に転調する101以降、テンポが速くなる。
第1主題に戻る150以降もpを維持。弦の二重フーガ風になる183以降、ppを保ちながらエネルギーをため、210以降のクレッシェンドで一気に開放。
第3楽章、ほぼ標準的なテンポ。軽快に進めていくが、Vがffでメロディを弾く91〜93だけは4分音符の1音1音を強調させる。ただ、同じ部分が2回目、3回目になると少し甘くなるのが惜しい。
トリオでテンポを速め、推進力を上げる。
間髪入れず第4楽章へ。ここもほぼ標準的なテンポ。軽快な流れの中に躍動感が加わる感じ。繰り返しても胃にもたれない。
展開部に入って136〜137のVと138〜139のVa以下のやり取りも、ガチンコでぶつかるのでなく、互いを尊重して強調するような雰囲気。
終盤の全奏、330のffは抑え目で336のffで全開。
館内の興奮を鎮めるかのように、アンコールはモーツァルトの上品な舞曲。
バーメルトの指揮は、音楽の流れは時にオケに任せながらも、どこでどのパートのフレーズを強調させるかを明確に指示しながら進めてゆくので、団員もわかりやすいだろうし、聴いている方も意図がよく伝わってくる。演奏中の団員同士のコミュニケーションもしっかり行われているようだ(特にコンマスと第2Vの首席のアイコンタクトが濃密)。誰かが力ずくで強引に持っていくような場面が全くなく、指揮者とオケの幸せな関係がそのまま音楽として結実している。なかなか見られるものではない。
今後このコンビの演奏がどう進化していくのか、さらに楽しみになってきた。
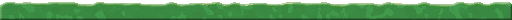
表紙に戻る