 エリソ・ヴィルサラーゼ(P)+アトリウム弦楽四重奏団
エリソ・ヴィルサラーゼ(P)+アトリウム弦楽四重奏団
○2017年11月28日(火)19:00〜21:25
○紀尾井ホール
○2階BR2列31番(2階上手側バルコニー2列目後方)
○モーツァルト「ピアノ四重奏曲第1番ト短調」K.478(約28分、繰り返し全て実施)、ショスタコーヴィチ「ピアノ五重奏曲ト短調」Op57(約35分)
シューベルト「弦楽四重奏曲第12番ハ短調」D.703(断章)(提示部繰り返し実施)、シューマン「ピアノ五重奏曲変ホ長調」Op44(約29分、繰り返し全て実施)
〇1V=ボリス・ブロフツィン、2V=アントン・イリューニン、Va=ドミトリー・ピツルコ、Vc=アンナ・ゴレロヴァ

秋の夜長の贅沢な室内楽
ヴィルサラーゼはソロ、協奏曲はもちろん、室内楽も得意な文字通りオールラウンダーである。ボロディンSQなどとたびたび共演してきたが、今回は若手の弦楽四重奏団でショスタコーヴィチなどに評価の高いアトリウムSQとの共演が実現。9割程度の入り。
前半はト短調の曲で揃える。
モーツァルトの第1楽章、3小節目までのfと4小節目のpの対比を明確に。過日の協奏曲のときと同じように、狭めの強弱の枠を守りながらその範囲で豊かな表情を付ける。後半の繰り返しも実施。
第2楽章、8分の3拍子だが8分の6くらいのフレーズ感で滑らかに進む。50以降のピアノとVaのやりとりが心地良い。
第2楽章が終わるとすかさず第3楽章へ。今までの音楽は「何でもない、気にしないで」と言わんばかりに、さわやかに軽やかに奏でられる。ただし、4〜8でスタッカートとスラーが8分音符2つずつ交互に出てくるところなどは正確に。
弦の中心に座る
ショスタコーヴィチのような重い曲を前半に持ってくるとは驚き。
第1楽章、ピアノがホールの空気を引き締めるような和音で始める。そこに加わる弦の響きも緊張感に満ちている。
第2楽章、静かだが息が詰まるような弱音で延々と続くフーガ。今度は1Vから始まり、弦の4人が発展させたところへピアノが加わる。響きに酔えるような余裕はない。むしろ息苦しさへの忍耐力を要求される。
第3楽章、第2楽章からは開放されるが、今度は一分の隙なく動く精密機械の中に放り込まれる。ピアノは自由奔放に鳴らすことは許されず、金属が決められた型にプレスされるような和音をしつこく繰り返す。弦のアンサンブルは、かみ合った歯車のうなりのように響く。
第4楽章、疲労困憊の中から救いを求めるようなメロディ。少しずつ響きを重ねながら発展していくが、クライマックスで歓喜の音楽とはならず、逆に断末魔の叫びとなる。
叫びが収まって第5楽章へ。ようやく穏やかで落ち着いた音楽になるが、果たしてこれは救いなのか諦めなのか。最後のピアノのフレーズがさりげなく、しかし尻切れトンボに曲を閉じる。
さすがにショスタコーヴィチが得意とあって、4人の弦とピアノががっちりかみ合い、ゾクゾクする。
後半はまずアトリウムSQのみの演奏。短い曲ではあるが、ショスタコーヴィチでエンジンがかかったのか、こちらも終始緊張感が保たれ、息の合ったアンサンブル。
シューマン第1楽章、テンポは速いが速さを感じさせない。冒頭2小節の和音には力強さだけでなく、花がふわっと開くような響きの広がりがあり、続く2小節における4分音符の連打もきっちりしているが煽る感じがない。9以降のピアノは一転して優しくしなやかに歌う。
57以降は低弦の聴かせどころなのだが、Vaは良く歌うがVcの音がこもりがちで弱い。
第2楽章も速いテンポ。ハ長調に転じる29以降は1VとVcのメロディよりも2VとVa、ピアノの動きの方を前面に。激しいヘ短調のアンサンブルを経て110以降にVaが復活させる第1主題が美しい。曲想が両極端に振れる場面がたびたび出てくるが、その変わり目で全くテンポを落とさず、次へ次へと進んでゆく。
第3楽章、明るく伸び伸びとしたアンサンブル。ここでも主部とトリオのあいだの間を取らない。トリオ2冒頭で1Vが落ちかけてヒヤリとする。
第4楽章は完全にピアノ主導で、弦は控え目。220以降のユニゾンでようやくピアノと弦が対等になり、あとは息も付かさず一気に弾き通す。ここでも、重厚な音楽の流れを保ちながら、気まぐれとも言うべきシューマン独特の曲想の変化を隙なく織り込んでゆく。
ヴィルサラーゼは今回も重厚さと繊細さを兼ね備えた見事な響き。一晩でピアノ付室内楽3曲を弾き通すスタミナにも脱帽。
アトリウムSQは1Vがいつものセルゲイ・マーロフでなく、ボリス・ブロフツィンに変更。そのせいかどうかはわからないが、SQ側はVaのピツルコがピアノとのつなぎ役を果たしているように聞こえる。
やはり秋の夜長は室内楽に限る。
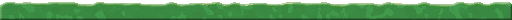
表紙に戻る