 スラトキン指揮デトロイト響
スラトキン指揮デトロイト響
○2017年7月17日(月・祝)15:00〜17:10
○文京シビックホール
○2階21列14番(2階最後列中央やや下手寄り)
○バーンスタイン「キャンディード」序曲、バーバー「弦楽のためのアダージョ」(15-13-9-10-7)
ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」+「エイジアン・ドリーム」(P=小曽根真)
コープランド「交響曲第3番」(約43分)
+菅野よう子「花は咲く」、フェリックス・スラトキン「悪魔の夢」
〇15-13-10-10-7(下手より1V-2V-Vc-Va,CbはVcの後方)

ヨーロッパ偏重の是正を
レナード・スラトキンは指揮者としては近年ほぼ毎年来日しているものの、自身が音楽監督を務めるオケと一緒に来る機会はこれまでほとんどなく、セントルイス響時代もワシントン・ナショナル響時代も確か1回ずつしか来ていないはずだ。ところが、昨年はフランス国立リヨン管と、今年はデトロイト響と相次いで手兵を率いての来日が実現。デトロイト響としても実に19年ぶりの来日となる。
2回の東京公演のうちオール・アメリカン・プログラムへ。ほぼ満席の入り。
久々の来日とあってメンバーのやりくりにも苦労したのか、弦のパートのうち1V,2V,Cbが奇数。もっとも米国のオケでは決して珍しいことではない。ヴァイオリンは見たところ14名ずつかと思ったのだが、よく見ると最後列は1人ずつ。しかも、2Vの最後列の奏者は前の奏者とHpを挟んでかなり離れたところに座っていて、隣の1V奏者の方が近いくらい。ヴィオラの最後列手前の奏者はなぜかバーバーのときだけ袖に下がる。練習不足で自信なかったのかしらん?
Hpも「キャンディード」の後一旦舞台袖に運び出し、後半再びステージに出すという念の入れよう。なお後半は2台。
打楽器が多いので下手後方に集められ、Hr5人は木管の後ろに横1列に並ぶ。その後方にTpが5人、上手に向かって横1列、さらにステージ奥の壁に沿うようにTbとTuが座るので、金管の列とVcパートの間にかなりのスペースができる。
バーンスタイン「キャンディード」序曲はびっくりするような大音量ではないが、軽快に進む。キラキラと輝く金管の響きが印象的。
バーバー「アダージョ」は、速めのテンポと明るい響き、滑らかなフレージングで美しいが悲しい感じは控え目。「葬送のために作った曲ではない」との作曲者自身の言葉に忠実な演奏。
ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」、ピアノはヤマハ。テンポは遅め。弱音器を付けた金管が音を狭めたり広げたりするところが何ともしびれる。小曽根のカデンツァも、頭の中であれこれ曲想を巡らせた後、じっくり熟成させてから音にしている感じ。後半ホ長調の部分に至る前のカデンツァでは、両手を交差させた状態で右手が低音で細かいフレーズを何度も繰り返す場面が印象的。ジャズのリズム感覚を守りながらも、時折禅問答的みたいな音楽の流れになるところも面白い。
アンコールもムーディーで題名通り夢見るような雰囲気の曲。
コープランドは日本でめったに演奏されない。せいぜい「アパラチアの春」「ロデオ」くらいか。ましてや交響曲はさらに演奏機会がない。第3番は1946年の作品だが、同時期に作曲されたショスタコーヴィチやプロコフィエフなどの交響曲に比べて、あまりにも冷遇されていると言わざるを得ない。
第1楽章、4度や5度の音型が目立つゆったりしたメロディが静かな中にも整然と進んでゆく。徐々に盛り上がっていくが、あくまで整然とした雰囲気は保たれている。肩を組んで頂上目指し黙々と登っていく感じ。金管のコラール風のアンサンブルが美しい。
第2楽章、Hrの上昇音型が高らかにホール全体を満たすのを合図に、賑やかな宴会が始まる。トリオは木管のアンサンブルが中心。いつの間にか元のどんちゃん騒ぎに戻る。
第3楽章、弦の息長いフレーズが重ねられる。緊張感はあるが、楽天的な雰囲気。弦が夕日のようにゆっくり沈んでいったところで、木管が「市民のファンファーレ」を吹き始め、第4楽章へ。アメリカ人ならここで心の中で絶対"Yes!"と叫ぶはずである。残念ながらこの曲も日本でまず演奏されない。
力強く前進する主題がフーガ風に組み合わされ、発展していくが、突如不協和音に遮られる。気を取り直し、再び立ち上がり、高みを目指してゆく。華々しく終わるが、拍手やブラヴォーのフライングなし。聴衆にブラヴォー。
スラトキンは「どうもありがとう」「はなはさく」と日本語で話して「花は咲く」。メロディが各パートに受け渡され、大編成のオケでも聴き応え十分に編曲されている。そして、最後にお父さんの曲を。悪魔が夢の中で大暴れしているような、陽気な曲。
ソリストや指揮者、コンミスに演奏後花束を渡したり、演奏会が終わると終わったことを知らせるアナウンスが入るなど、昔の公共多目的ホール風のやり方が懐かしさを感じさせる。
デトロイト響はいかにもアメリカのオケらしい、明るい響きの弦と軽めだがパワフルな管が特徴。そこにスラトキンの指揮でアンサンブルの精度を磨くことで、トップクラスのオケへと成長させる。
依然として条件面の難しさはあるだろうが、我が国のクラシック界におけるヨーロッパ偏重を是正するためにも、この組合せでの再来日を今から期待したい。日欧・日米間の通商貿易問題よりよほど簡単なはずである。
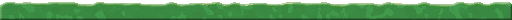
表紙に戻る