 長島剛子・梅本実リートデュオ・リサイタル
長島剛子・梅本実リートデュオ・リサイタル
○2016年11月4日(金)19:00〜20:55
○東京文化会館小ホール
○O列32番(15列目中央)
○フランツ・シュレーカー「お化け」Op7の4、「ああ鐘よ、恐ろしい鐘よ」Op5の1、「この子が天使になるように」Op5の2、「バラの死」Op7の5、「森の孤独」
ヴィルヘルム・グロース「愛の歌第2集」Op22より「お前のほっぺ」「素敵な夏が来たら」「パタン、パタン、開けておくれ」「水は流れ」「私はある若者が好きになった」「結婚式とは…」
コルンゴルド「5つの歌曲」Op38より1.「幸せを祈る」、3.「古いスペインの歌」、「3つの歌曲」Op22(「君は私にとって?」「君とともに沈黙する」「世は静かな眠りに入った」
ツェムリンスキー「妖精の歌」Op22の4、「いまだにきみの息を頬に感じている」「きみには聴こえなかったのか」「ふたり」
ヴァイル「ハッピー・エンド」より「マドロス・タンゴ」「ビルバオ・ソング」、「光の中のベルリン」
+マーラー「若き日の歌」より「夏に小鳥はかわり」、山田耕筰「この道」、シェーンベルク「キャバレー・ソング」より「ギガルレッテ」
○S=長島剛子、P=梅本実

忘れられた宝庫の扉を開ける
毎度お馴染み、「世紀末から20世紀へ」と題したリート・リサイタル・シリーズの15回目。今回は「ユダヤ人作曲家の歌曲を集めてVol.2」と題し、5人の作曲家を取り上げる。
7割程度の入り。
今回は初めての試みとして、前半と後半の演奏前に作曲家と曲目の紹介がアナウンスで流れる。演奏をより楽しむ上でもいい企画だと思う。
前半の長島さんは深緑を基調にした衣裳。
シュレーカーは1920年代にリヒヤルト・シュトラウスと並ぶ名声を得、ベルリン音楽大学の学長まで務めながら、ナチス政権の成立後その地位を追われ、34年失意のうちに死去。彼の作品は演奏禁止とされて長らく忘れられてきた。
「お化け」はいきなりピアノが高音の細かいパッセージを響かせ、聴く者を不思議な世界へ誘う。しかし、途中からワルツのリズムとなり、お化けたちが空中を軽やかに踊る。
かなり長い間を置いて2曲目へ。陽気なお化けの踊りから子どもの死を題材にする曲に変わるのだから、当然だろう。
「ああ鐘よ、恐ろしい鐘よ」はD−Cis−A−Hの鐘を表す音型が不気味に響く中、悲しみに沈むメロディが切々と歌われる。
「この子が天使になると」は長調に転じ、清らかなメロディと和音に乗って、亡き子が天国へ昇るよう切々とした祈りが歌われる。
「バラの死」はピアノでオクターブを越える跳躍が随所に現れる一方、スローモーションのようにバラの花が萎れていく。
「森の孤独」はホ長調、ピアノの細かいフレーズが左右で重ねられて独特の響きを醸し出す。恋人同士が夜の森の中を散策するのだが、どこか楽しそう。
グロースはシュレーカーの弟子。作曲家としてだけでなくレコード会社のマネージャーとしても手腕を発揮したが、ナチスの弾圧を受け、イギリスを経てアメリカへ亡命。ポピュラーの作曲者として「ハーバーライト」「夕日に赤い帆」「カプリ島」といったヒット曲を生み出すも、1939年45歳の若さで亡くなる。「ハーバーライト」はプラッターズ、「夕日に赤い帆」はナット・キング・コール、「カプリ島」はフランク・シナトラなどが歌っているのを今でも聴くことができる。前の2曲はハワイアンを思わせるムーディな歌、「カプリ島」は陽気な失恋の歌だ。
これに対して「愛の歌第2集」は東ユダヤ民謡のテキストに基づくもの。「お前のほっぺ」や「素敵な夏が来たら」は素朴なメロディとリズムが印象的。
「パタン、パタン、開けておくれ」はピアノがFisの連打で、男が恋する女の家の扉を叩き続ける。しかし、女はつれなく応対。
「水は流れ」は行進曲風。しかし、内容は他愛のない恋愛物語。
「私はある若者が好きになった」は、ロマンチックなメロディがふんだんに使われ、オペラ風に進行する。愛する男を失った女の嘆きの歌。
「結婚式とは…」は陽気な音楽、民族のエネルギーが爆発するが、最後のピアノの増8度の不協和音にハッとさせられる。
後半の長島さんは黒と金を織り交ぜた衣裳。
コルンゴルドは最近日本でも演奏される機会が増えてきた。しかし、歌曲を生で聴くのは初めて。
最初の2曲は映画音楽の一部として書かれたもの。「幸せを祈る」はホ長調のメロディがー瞬変ホ長調に転調する。「古いスペインの歌」は少女が失われた愛を懐かしむ歌だが、映画の挿入歌にしては正統的な歌曲の風格がある。
「3つの歌曲」は亡命前の作品。「君は私にとって?」は、コルンゴルド得意の4度上がって伸ばす音型が多用され、「死の都」のマリエッタのアリア「私に残された幸せは」を思い出させる。「君とともに沈黙する」「世は静かな眠りに入った」は共に愛の高揚を音楽で表現。前者ではハイCが登場し、後者も終盤でメロディが急激に上昇し、まるで鳥が飛び立つようなフレーズで終わる。
ツェムリンスキーは今回取り上げられた作曲家の中では最も早く生まれ、シェーンベルクが唯一師と仰ぐ人でもあった。彼自身は12音技法へ踏み込まなかったとは言え、作品からは調性の崩壊を思わせる危うさが伝わってくる。
「妖精の歌」はゲーテの詩によるものだが、目まぐるしい転調が聴く者を不安に陥れる。
2曲目以降はホフマンスタールの詩による。「いまだにきみの息を頬に感じている」では半音階が多用され、「きみには聴こえなかったのか」でも不協和音の連続の末、ようやく最後の和音で調性の世界に戻ってくる。「ふたり」は物語風の音楽で、4曲の中では最もわかりやすい。女が男に盃を渡そうとする話で、後のシュトラウスのオペラ「薔薇の騎士」の原型とも言うべきエピソード。
最後はヴァイル。最初の2曲は音楽劇「ハッピー・エンド」のナンバー。長島さんは一転してリラックスした表情。「マドロス・タンゴ」はピアノに右肘を付いた格好で歌い始める。「ビルバオ・ソング」ではステージの上を歩き回りながら歌い、途中でピアノを弾く梅本さんの椅子に腰かけ、頭を彼の肩に乗せかける。思わず手拍子を打ちたくなる。
「光のベルリン」は1928年にベルリンで開かれた同名の祭典のために書かれたが、キャバレー・ソングを思わせる。
アンコールはまずユダヤ人作曲家ということでマーラー、次に「知っている曲がなかった」では困るので、日本語の歌。最後はやっぱりユダヤで締めようということで、シェーンベルクのキャバレー・ソング。
今回の選曲の影響もあると思うが、長島さんはいつもよりは抑え気味の表現が目立つ。悲劇的な最期を迎えた作曲家たちに対する深い思いが伝わってくる。その分最後のヴァイルで身振り手振りも交え、伸び伸びとした歌い上げる。
これも毎度のことながら、梅本さんのピアノも見事。いつも以上に繊細な表現が求められる場面が多かったが、柔らかな音色としなやかなフレージングで長島さんの歌を支える。長い前奏を伴う曲もいくつかあったが、歌へつなげるまでの雰囲気作りも絶妙。
2人のアンサンブルが、忘れられていた名曲の宝庫の扉を開け、私たちに感動と喜びを与えてくれる歌曲がまだまだたくさんあることを知らせてくれた。今後とも彼らの「発掘」作業が順調に進み、その成果をまた聴くことができる日が、今から待ち遠しい。
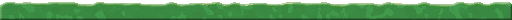
表紙に戻る