 レナード・スラトキン指揮N響(Aプロ)(2回公演の2回目)
レナード・スラトキン指揮N響(Aプロ)(2回公演の2回目)
○2016年4月17日(日)15:00〜16:50
○NHKホール
○3階L10列29番(3階10列目下手寄り)
○バッハ「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調」BWV1006より前奏曲(V=伊藤亮太郎)
同「カンタータ第29番」(神よ、あなたに感謝をささげます)BWV29より「シンフォニア」
同/ウッド「組曲第6番」より終曲
同/バルビローリ「カンタータ 狩りだけが私の喜び」BWV208より「羊は安らかに草を食み」
同/オーマンディ「カンタータ第147番」(心と口と行ないと命)BWV147より「主よ、人の望みの喜びよ」
同/ストコフスキー「トッカータとフーガニ短調」BWV565
プロコフィエフ「交響曲第5番変ロ長調」Op.100(約46分)
(16-14-12-10-8、下手より1V-2V-Vc-Va、CbはVcの後方)
(コンマス=伊藤(前半)、篠崎(後半)、第2V=田中?、Va=佐々木、Vc=向山、Cb=西山、Fl=神田、Ob=青山、Cl=伊藤、Fg=水谷、Hr=今井、Tp=菊本、Tb=栗田、Timp=植松)

"Very Slatkin"なプログラムを満喫
4月のN響定期に、今や米国を代表する巨匠となったスラトキンが登場。前回はおととしに予定されていたが、急病のためキャンセルとなった。そのため、意外だが4年ぶりの来日となる。8割程度の入り。
今回は3つのプログラムを担当するとあって、それぞれに彼の意気込みが十分伝わってくる。特にAプロは、前半にバッハの編曲物を並べるという、彼でなければ考え付かないような選曲。珍しくプログラムに「すなわちバッハとは(Bach
in other words)」と題されたスラトキンのメッセージが挟まれている。バッハが生きていた頃と異なり、オルガンで演奏される機会がめったになかった時代には、管弦楽による編曲を通じて多くの人々がバッハの音楽を知ったことが紹介され、そのような作品を並べてみたとのこと。
米国での演奏会はこの内容を彼が演奏会の冒頭で聴衆に語り掛けたはずである。我が国でもようやく彼の音楽活動のスタイルの一端が伝わるようになり、素直に嬉しく思う。
この日はオケの団員が全員ステージに揃い、指揮者が登場すると、まず指揮台の横に立つ。コンサートマスターの伊藤が立ち上がって、無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番の前奏曲を颯爽と演奏。演奏が終わるとさっきまで使っていた譜面台を下げ、以後は第1列(プルト)の奏者用の譜面台として使用。
カンタータ第29番の「シンフォニア」は、今の前奏曲をニ長調にして管弦楽用にバッハ自身が編曲したもの。オルガンが加わり、弦は第1Vから4-4-3-3-2の編成、つまり前の方の人たちだけ演奏し、あとはObとTp(もちろんバロックTp)とティンパニが加わる。ティンパニも上手後方端に置かれた小さいものを使う。
続いてウッド編曲のものは、やはり同じ前奏曲を弦楽合奏と木管用にしたもの。弦は全員が弾き、木管・金管は3管編成。調性はホ長調のまま。ヴァイオリン奏者は全員オリジナル通り弾く一方で、他のパートが和音を補強したり、ヴァイオリンのフレーズを繰り返したり重ねたり、豊かなアンサンブルに。カーテンコールではヴァイオリン奏者たちを立たせる。
「羊は安らかに草を食み」は弦楽合奏にFl4、Ob,EHr,Fgが各2という、オリジナルに近い編成。ほのぼのとした曲想が何とも心地よく、抑え気味の弦の上で木管がのんびりと歌っている。カーテンコールでは木管奏者たちを立たせる。
「主よ、人の望みの喜びよ」は弦楽合奏のみの演奏。合唱パートは主にVcが担当。こちらは終始流麗なアンサンブル。最後は静かに終わる。
そしてバッハの編曲物の代表作と言うべきストコフスキー編の「トッカータとフーガ」。繰り返される冒頭の主題を遅めに、念押しするように響かせる。大編成の管弦楽が分厚い和音を鳴らし、原曲のスケールの大きさを効果的に表現。トッカータの最後の音が残った状態でフーガヘ突入。最初の主題だけでなく、それに応える主題も対等に強調しながら音の大伽藍を築いてゆく。
バッハ自身が自分の作品を他の作品用に編曲していたことを示した上で、主に20世紀前半の指揮者たちが、それぞれの曲に合った編成で多様に編曲していたことを紹介していく。実に面白いし、オケのレパートリーとして再評価してもいいのではないか?
後半はプロコフィエフの交響曲の中で「古典」に並ぶ人気の第5番。前半は全て譜面を見ていたが、後半は暗譜。
第1楽章、12小節以降の弦のアンサンブル、コンサートマスターが篠崎に替わった途端に、響きが「まろ」やか、いや艶やかに。83以降の1VとVcなどによる細かいフレーズは尖った感じよりレガート重視。木管と弦が主導する音楽に金管・打楽器が加わることで次第にハーモニーが成長していく。特に241以降弦と金管が大地の根っこから空に向かって伸びる大木のような音楽を聴かせる。
第2楽章、冒頭2小節の1Vのp<f>mPに至る山もきっちり作り上げる。3以降、Cl→Ob+Va→Vc→1Vへとメロディの受け渡しも実に自然でスムーズ。
トリオでは112〜119の部分が、120〜215の部分をサンドイッチするような構成。同じニ長調だが曲想がかなり変わるが、この変化もはっきり付ける。
スケルツォ主部に戻って終盤、313以降は1小節ごとに、4個の四分音符をだんだんクレッシェンドしては、少し落としてまたクレッシェンドするといった動きを繰り返して最後の和音に至る。
第3楽章、1Vの細かい三連符の連続を、おぼろげながらも輪郭をはっきりと響かせる。9以降の悲痛なメロディは、1Vよりも1オクターブ下を弾くVaの方を大きめに聴かせる。この楽章も金管と打楽器が加わる後半のクライマックスに至るまで、息の長い音楽が続く。
これぞ静謐と言うべき響きで第3楽章を締めくくると間を置かずに第4楽章へ。Clの伸びやかだが少し呑気な感じの第1主題に対し、36以降1Vが少しイラついた表情で絡む。
ロンドの主題と間に挟まる部分との曲想の切り替えも明確。特に終盤に再現されるフレーズが最初に登場する164以降の低弦が表情豊かに歌う。
その後は目まぐるしいfとpの入れ替わりを忠実に聴かせながら全体を盛り上げ、最後はスピード感と重厚さを兼ね備えたフィナーレに。
テンポは各楽章ともほぼ標準的。大きな音楽の流れを終始保ちながら、皮肉っぽいフレージングや攻撃的な響きを極力抑え、この曲に秘められた美しい部分あるいは気品に満ちた部分を最大限に浮き立たせようとする工夫が随所に見られる。
カーテンコールではCl首席の伊藤を立たせる。指揮者への団員たちの拍手が2回。
終演後マエストロにプログラムのことを聞くと、"Very Slatkin"という答えが返ってきた。確かに、彼でなければ考え付かないようなプログラムである。また、バッハとプロコフィエフを組み合わせた意図を尋ねると、「バッハと言っても大管弦楽の華麗な響きも出てくるので、その流れで選んだ」とのこと。確かにストコフスキーとプロコフィエフの組合せは、編曲と作曲という違いはあれ、20世紀前半の作風の一側面を象徴的に聴衆に伝える上で効果的であることは間違いない。
とにかくマエストロが元気な姿で日本の聴衆の前に戻ってきたことを喜びたい。あとのプログラムも楽しみ。
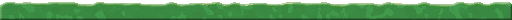
表紙に戻る