 ザ・プロデューサー・シリーズ 木戸敏郎がひらく「20世紀の伝言」
ザ・プロデューサー・シリーズ 木戸敏郎がひらく「20世紀の伝言」
○2014年8月28日(木)19:00〜21:00
○サントリーホール
○2階LC4列8番(2階下手中央寄りのサイド4列目)
○シュトックハウゼン「リヒト」より「歴年(1977)」(雅楽版)
笙=宮田まゆみ、石川高、東野珠実、龍笛=芝祐靖、笹本武志、岩亀裕子、篳篥=中村仁美、八百谷啓、田渕勝彦、鉦鼓=神田佳子、鞨鼓=山口恭範、太鼓=菅原淳、楽筝=福永千恵子、琵琶=佐藤紀雄
奉行=西村高夫(銕仙会)、舞人:松井北斗、笠井聖秀、山田文彦、小原完基、他
音楽監督=木戸敏郎
共同演出=木戸敏郎、佐藤信
一柳慧「時の佇まい 雅楽のための」(世界初演、サントリー芸術財団委嘱)
笙、う(竹かんむりに干)=宮田まゆみ、石川高、東野珠実、三浦礼美、中村華子、村岡健一郎、龍笛=笹本武志、岩亀裕子、篳篥=中村仁美、八百谷啓、田渕勝彦、大篳篥=溝入由美子、箜篌=佐々木冬彦、軋筝・十七絃筝=福永千恵子、多井智紀、中澤沙央理、打物=神田佳子、山口恭範、菅原淳

時を刻むのは数学か自然か
8月末の風物詩、サントリー芸術財団主催のサマーフェスティバル。昨年から1人の総合プロデューサーに企画監修を依頼するというスタイルを始めたが、今年は元国立劇場演出室長で、雅楽を中心に斬新な公演をプロデュースし、古代の楽器の復元と進化に取り組んでいる木戸敏郎が登場。彼が国立劇場開場10周年記念作品として委嘱したシュトックハウゼンの「歴年」を、初演時の楽器編成=雅楽版と、その後「リヒト」という大作オペラ(全体を上演すると29時間かかるという)の一部として改作された洋楽版で上演するという。伝統芸能を公演する国立劇場が前衛音楽のトップランナー的存在のシュトックハウゼンに委嘱したというのも驚きだが、初演後の評価が芳しくなく、その後再演されないまま今日に至っているというのも残念な話である。それがこのような機会に復活するというのは非常に意義のあることだし、関係者の英断をまずは大いに歓迎したい。
PブロックとLA,RAブロックの大半が閉鎖され、7割程度の入り。
舞台はいつもの演奏会とは全く異なる設定になっている。Pブロックに巨大スクリーンが置かれ、舞台後方には奏者たちの席、その後ろに数字の表示板が4つ。舞台の床には「1977」と白い太字で描かれている。
下手から小袖に袴姿の奉行が登場し、彼の合図で奏者たち、舞人たちが入場。舞人は平安貴族風の衣装に蔵面(長方形の紙に墨で描かれた面)を付け、「1977年」のプラカードを持った人に先導されて登場し、床の上の数字のそれぞれ書き始めの位置に立つ。プラカードは下手手前端に立てられる。
千の舞人の後ろには3人の笙、百の舞人の後ろには3人の龍笛と鉦鼓、十の舞人の後ろには3人の篳篥と羯鼓、一の舞人の後ろには楽筝、琵琶と太鼓。(楽筝の奏者が一旦舞台袖に下がり、しばらくして戻ってくる。演奏が始まってしばらくするとスタッフが出てきて奏者に何事かささやいていた。何か演奏する上で不都合があったのかもしれない。)
奉行が能の口調で作品の紹介をし、上手端へ移動。
音楽が始まると一の位の舞人(以下「一の舞人」、以下同様)はせわしなく「7」の字の上を行き来する。十の舞人はそれより少しゆっくり、百の舞人はさらにゆっくり、千の舞人はほとんど動かない。舞人の動きに合わせて掲示板に下から上へ数字が表示される。一の位は3〜4秒ごとに1から進み、7まで行くとまた1に戻る。十の位はそれよりゆっくり数字が表示され、やはり7まで行くと1に戻る。百の位はさらにゆっくり表示され、千の位は何も表示されない。
また、彼らの動きはスクリーンにモノクロ映像として示される。舞台を上から映し、舞人たちが動くとその軌跡が白い影のように残り、次の動きをすると前の影は消えて新たな影が映される。
277年まで来たところで上手から学校のチャイムのような鐘が鳴り響き、黒の上下の男3人が入ってくる。舞人たちは止まり、音楽も笙以外は止まる。男の1人はバラの花束を持っていて、舞人たちに渡そうとする。しかし、一の舞人も十の舞人も百の舞人も首を横に振る。千の舞人は完全無視。怒った男は花束を床に投げつけ、去ってゆく。この間スクリーンには上手側から悪魔のイラストが現れるが、男たちが去ると悪魔も退場。入れ代わりに下手側から天使のイラストが現れる。(以下同様に、妨害のシーンでは悪魔、元に戻すシーンでは天使が登場。)下手から天使風の白い衣装の少女が現れ、舞人たちを拍手で励ますよう客席に促す。舞人たちは再び舞い始める。しかし、すぐに十の舞人と一の舞人は止まり、百の舞人だけが動く。
しばらくすると全員がそれぞれの動きで舞いを再開してするが、363と474の間になったところで、上手から鈴が鳴る。ワゴンに乗せた料理が運ばれ、上手手前で止まる。男がふたを開けると山盛りのソーセージ。一、十、百の舞人が近寄って食べようとする。千の舞人は動かず、逆に誘われても戻るように指示。下手からライオンが現れ、一、十、百の舞人たちを追い払うが、一の舞人は赤くて細い棒を持ち帰り、次の舞でも使う。
舞人たちが舞を再開し、523年まで進むと、今度は上手からクラクションを流しながら赤い耳のゴリラがバイクに乗って乱入してくる。一、十、百の舞人たちはまたも引き寄せられ、ゴリラの真似をしてバイクに手をかけてポーズを取ったり、クラクションを鳴らしたりする。千の舞人もこらえきれずに近付いて行くと、少女の天使が1千億円札(シュトックハウゼンの肖像付)をプラカードのように掲げて登場し、舞人たちを元の場所へ返す。バイクは走り去り、1千億円札は奉行が座る上手端に立てかけられる。
舞人たちが舞を再開し、666年まで進むと、上手からラジオの音楽に乗って黒いコートを羽織った美女を乗せたワゴンが登場。赤い靴を1足ずつ脱いで投げ捨て、女は舞人たちに向かってコートを左右に広げて身体を見せる(実際には黒の下着姿。残念(何が?))。これにはさすがに舞人たち全員が動揺するが、そこで雷鳴が轟き、稲妻が落ちる。
舞台は暗闇となり、そこから舞を再開。天井の裸電球1つの光から徐々に明るくなり、数字の表示も1977に近付いてくる。すると、舞台前方に男2人が現れ、白い紐をゴールテープのように伸ばして両脇に立つ。そこに向かって4人の舞人たちはゆっくりなだれ込むような姿勢を取る。
演奏が終わると奉行が中央に進み、37年前の初演の時にも演奏した唯一の奏者である龍笛の芝祐靖さんに花束を贈呈。そして、締めの舞を披露。
時を刻む舞と音楽は数学的ルールに基づき緻密に展開されるのに対し、それを悪魔がたびたび邪魔しようとするが、その都度天使が助け舟を出す。ただ、最初の拍手はともかく、ライオンや雷鳴で脅したり、金で釣ろうとしたり、手法としては悪魔と大差ないようにも見え、善悪の相対性を暗示しているようにも見える。
誰にも影響されない絶対的存在のように見える時が、実は世俗の誘惑に流されやすい人間臭い存在であると言うべきか。言い換えれば、人間が感じる時(人生の様々な場面で時が早く流れることもあれば止まったように感じることもある)を視覚化、音楽化したということか。
後半は一柳慧が「歴年」にヒントを得て、彼なりの時の捉え方で作曲した新作。舞台中央前方に軋筝、十七絃筝、箜篌、後方に打物、上手に笙と?、下手に龍笛、篳篥、大篳篥が長方形状に並ぶ。
打物が拍子木のきざみ風に打っていくのを合図に音楽が動き始める。笙の宮田まゆみが客席から吹き始め、ゆっくり移動しながら舞台に上がり、上手端に合流。その後も打ち物のきざみを合図に龍笛、篳篥、大篳篥が合奏したり、箜篌、軋筝、十七絃筝(軋筝と十七絃筝の1人は終始弦楽器の弓を使って演奏)が合奏したり、基本的には長方形の各辺のグループが一体的となって演奏しているように聴こえる。そこには、シュトックハウゼンのように規則的に刻む時ではなく、一つの事象が他の事象を引き起こし、それがさらに次の事象を引き起こすといった、より自然発生的な時の動きというか、文字通り時の「流れ」を感じさせる。合奏が盛り上がるところでは電子音楽も加わっているようだ。最後は各奏者の動きが一つの音の塊となって集約されて終わる。
見たことはあるが名前は知らない楽器、名前は知っているが見たことのない楽器、名前も知らないし見たこともない楽器もあり、それらを見て音を聴くだけでも面白かったが、不協和音やクラスターなど、西洋の作曲家が20世紀に入ってから注目し出した要素が、雅楽の楽器の場合は古代から当たり前のように取り入れられていたことに、今さらながら気付く。だから、新作であってもどこか聴いたことがあるような感じがする。親しみまでは感じないが、音楽として距離的に近い感じがする。日本人として当たり前のことかもしれないが。
30日の洋楽版「歴年」を聴くと、また違うことを感じるかもしれない。
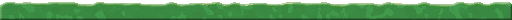
表紙に戻る