 フランチェスコ・トリスターノ(P)
フランチェスコ・トリスターノ(P)
○2013年2月20日(水)19:00〜21:10
○王子ホール
○C列15番(3列目中央やや上手寄り)
○トリスターノ「プレリュード」、ブクステフーデ「アリア「ラ・カプリッチョーザ」32の変奏曲ト長調」BuxWV250(繰り返し全て実施)、同「トッカータ ニ短調」BuxWV155、同「組曲ニ短調」BuxWV233、トリスターノ「ラ・フランシスカーナ」
バッハ「パルティータ第3番イ短調」BWV827、「同第5番ト長調」BWV829(いずれも繰り返し全て実施)、トリスターノ「ベース〜シャコンヌ〜」
+トリスターノ「メロディ」、バッハ「ゴールドベルク変奏曲」より第30変奏、アリア

カッコいいバロックと現代を行ったり来たり
とにかくチラシの写真を見て驚いた。ピアノから後ずさりするように飛び上がっているのか、それともスパイダーマンのように壁に張り付いた態勢からピアノに向かって飛び降りようとしているのか。ルクセンブルク生まれのピアニスト、フランチェスコ・トリスターノはバロックと自作を含む現代物をレパートリーと定めて演奏活動を展開しているが、2010年の初来日以来我が国でも注目され、「グールド以来の衝撃」と評する人もいるようだ。前売りは完売、ほぼ満席の入り。
ステージ姿がこれまた珍しい。紺のジャケットとズボン、首元の開いた黒シャツに黒スカーフを巻き、長身かつ8頭身の美男子。これからファッション・ショーが始まると言われても疑問は持たないだろう。しかし、これはピアノ・リサイタルである。
まずは自作の「プレリュード」、真冬の朝の凍りついた湖を思わせる高音の澄んだ和音から始まり、ゆったりしたフレーズを繰り返しながら少しずつ変形させるという、典型的なミニマル・ミュージックのパターン。しかし、終盤でバロック風の―節が顔を出す。
と思う間もなくブクステフーデの変奏曲の主題が始まる。最新のCD「ロング・ウォーク」に収録した曲である。アクセントに今ひとつ鋭さがなく、弱音で速いフレーズを弾く部分もつながってはいるのだが、もう一息なめらかに流れない。ついピアノ(ヤマハ)のせいにしたくなる。テンポの幅もそれほど大きくはない。細かい表現にこだわる風にも聞こえない。バッハの「ゴールドベルク変奏曲」との共通点はよくわかるが、演奏としてびっくりさせられるようなものではない。
「トッカータ」も激しく短いフレーズの後に休符が入るという意味でバッハのニ短調の作品と似ている。休符を一呼吸長く伸ばすことで緊張感を高める。
「組曲ニ短調」もバッハのパルティータを先取りするような作品だが、どの舞曲の冒頭のメロディも似ているので、変奏曲風にも聞こえる。どの曲も流れがスムーズで心地よい。
ブクステフーデをピアノで演奏するのは珍しいとのことだが、そういう意味での違和感はない。
またも間髪入れず自作の「ラ・フランシスカーナ」へ。裏拍で7拍子を刻みながらDとFの間を行き来するメロディとFとAの間を行き来するメロディの繰り返しで曲は進む。バロックと現代の舞曲を対比させながら聴かせるということか。
後半はバッハのパルティータが2曲。3番は冒頭から淀みない流れ。fとpの頂点を抑え目にした強弱の中で弾いているのだが、前半はそれが中途半端な表現に聴こえたのに、バッハではいい塩梅に収まっている。「クーラント」の付点のリズムも軽やかだし、「サラバンド」の3連符の連続も少しもうるさくない。「ジーグ」におけるメロディーの追いかけっこも歯切れがよい。
5番ではやはり前奏曲2,4小節目の3拍目の休符と言うか、間の取り方が独特。聴く方を少しもてあそんでいるような感じすらする。「アルマンド」以降もスイスイ流れていくが、右手の1音と左手の2音の組合せで進む「メヌエット」における右手と左手の音量のバランスが絶妙。右手がつなぐメロディはもちろんきちんと聴かせた上で、これに応える左手の2音も出過ぎず引っ込み過ぎず、という感じで伴奏を務める。
さすがにバッハでは1曲弾き終えるごとに退場。
最後の「ベース〜シャコンヌ〜」は、これまでに聴かれなかった不協和音がミニマル風に繰り返される。後半ではピアノ内部の梁と弦を平手で叩き続ける。終盤は中音域の不協和音の連打を繰り返し、尻切れトンボに終わる。「シャコンヌ」という副題が付くからには全体を通じるテーマ的なものが隠されているのだろう。今夜の作品の中でも最も「現代音楽」風だが、それでもバロックとの接点をどこかで保っているのかもしれない。
アンコールの「メロディ」は「プレリュード」に近い曲想の癒しの音楽。そして、お決まりと言うべきか、CDに収録した「ゴールドベルク変奏曲」の第30変奏とアリアを披露。
少なくとも今晩のバッハを聴く限りでは、気をてらった表現は全くと言っていいほど見当たらない。しかし、弾き振りが何ともスタイリッシュと言うか、カッコいいのである。このあたりが彼の個性、才能のなせる業なのだろう。人気の秘密はこの辺にあるのかもしれない。
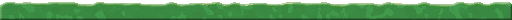
表紙に戻る