 ラトル指揮ベルリン・フィル(3回公演の初日)
ラトル指揮ベルリン・フィル(3回公演の初日)
○2011年11月22日(火) 19:00〜20:45
○サントリーホール
○2階RA5列23番(2階ステージ下手側5列目奥)
○マーラー「交響曲第9番ニ長調」(約84分)
(16-14-12-10-8)(下手から1V-Va-Vc-2V、Cbは2Vの後方)
(首席奏者:コンマス=樫本、第2V=スターデルマン、Va=シュックス、Vc=クアント、Cb=マクドナルド、Fl=ブラウ、Ob=マイヤー、Cl=オッテンザマー、Fg=ダミアーノ、Hr=ドール、Tp=タルケヴィ、Tb=オット、ティンパニ=ヴェルツェル)

ぬるさを追いやった個人技
ラトル指揮ベルリン・フィルが3年ぶりに来日。前回はコンマスの安永さん最後の公演となったが、今回は樫本さんがコンマスとして初の日本公演となる。当然ながらほぼ満席の入り。ヴィオラの次席に清水さんも座る。
マラ9は既にCDも出ているが、それを聴く限り全体的にぬるい感じが拭えなかった。この曲はカラヤンが晩年満を持してレパートリーに取り入れた曲だし、かつてはバーンスタインとの一期一会の名演もあったし、アバド時代にも94年に日本で演奏している。ベルリン・フィルにとって特別な曲と言ってもいい。それをラトルがさらに一段高めるのか、それともそんな過去の経緯とは決別するのか。期待と不安が入り混じる。
第1楽章、遅いテンポだが、今ひとつ緊張感が足りない。CDどおりの演奏。アバドの時にはVaを1Vの対面に置いたので、47小節以降の1Vに応えるフレーズが強烈に聴こえたのだが、この日は浮き出てこない。80以降少しテンポを上げるが、104以降の山もサーッと通り過ぎる。しかし121以降のBClは聴き応え十分。127〜129のTbのffからpへの下降音型はおとなしい。2回目の山に入ると186と190のティンパニが強烈。ほとんどdimをかけない。次の山が始まるきっかけとなる279では2VとVaが1VとVcのメロディをせき立てるかのように飛び込んでくる。ただ308以降頂点から奈落へ落ちていく場面はあまり深刻な雰囲気にならない。331以降のVも緊迫感が足りない。337以降出てくるグロッケンシュピールは、鐘の後ろにスピーカーのような箱が付いている。381以降のブラウ(Fl)のソロでようやく枯れた雰囲気に。テンポは山の部分で少し上げては、主旋律が戻る場面で元に戻す感じ。
第2楽章、やや遅め。穏やかな感じで始まるが、9の2VのメロディでG−A−Hの3つの音を思いっきり刻ませる。13以降たびたび登場するHrのトリルだが、ときどき少し音を延ばしてからトリルに入る。90以降ワルツ風の部分でテンポを上げる。第1楽章の主題が回想される218以降はあまりテンポを落とさない。その後も基本的にはこのパターンだが、423以降はさらに速くなり、あおられる感じに。ただ、時折バラバラっとしたアンサンブルになる。
第3楽章、出だしはCDほど速くない。一歩ずつ踏みしめながら進む感じ。しかし、180以降シンバル一発で一気に緊迫感が高まりる。357のシンバルで再び雰囲気が変わるが、テンポを速いまま変えないので、第4楽章の主題が出てきてもせわしない感じが続く。484以降のVaソロでようやく落ち着くが、すぐまたテンポを上げるので、522以降終盤のクライマックスに向かう場面で緊張が効果的に高まらない。
第4楽章、やや遅め。これまで影が薄かったVaがようやく存在感を発揮し始め、弦の響きが格段に充実。13以降1Vのメロディに絡む弦の4分音符と16分音符4つのフレーズの間をはっきり切るのが印象的。40以降の樫本のソロも美しい。後半のクライマックスも効果的な盛り上げを聴かせ、118のティンパニも背筋が伸びるような強烈な一撃。122でVだけ残るところも緊張が保たれたが、126で他のパートが加わるところが、こわごわ入る感じに。しかし、その後は張り詰めた空気を維持したまま徐々に消えていく。振り終わったラトルは指揮棒の先に左手で添えた状態で静止、かなり時間が経ってからゆっくり腕を下ろす。聴衆もそこまで拍手を待つ。
最初のうちはCDどおりの演奏かと思ったが、特に木管がピッコロからコントラ・ファゴットまで次々と名人芸を聴かせると団員同士が刺激し合う形になり、響きが充実。第4楽章ではこれぞベルリン・フィルという重厚感に身を委ねることができた。
しかし、そうなるとますますラトルの振る意味が薄れてくるような気がしてならない。何のために彼はいるのか?例えば第4楽章142〜144にかけてVが日没前の最後の輝きを放つところなど、なぜもう一息オケを追い込まないのか?
団員が退場した後も鳴り止まぬ拍手の中、呼び出されたラトルは樫本も呼び出す。殊勲のコンマスが照れながらさっさと退場した後、一人残された指揮者の姿は図らずもベルリン・フィルの現状を象徴しているのかもしれない。
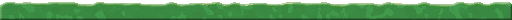
表紙に戻る