 メキシコ音楽祭2011 アドリアン・ユストゥス(V) ヴァイオリン・リサイタル
メキシコ音楽祭2011 アドリアン・ユストゥス(V) ヴァイオリン・リサイタル
○2011年1月13日(木)19:00〜21:25
○紀尾井ホール
○2階C3列23番(2階中央3列目上手端)
○シェリング「古典的前奏曲」、ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調」Op47(クロイツェル)(約37分、第2楽章繰り返し実施)、イザイ「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番イ短調」Op27
M.M.ポンセ「ソナタ・ブレーヴェ」、パガニーニ「カプリース集」作品1より第5,21,13,6,15,1,17番、同「ラ・カンパネラ」
+M.M.ポンセ「エストレリータ」、サラサーテ「サパテアータ」、ドヴォルザーク「スラヴ舞曲ホ短調」Op72の2
○P=ラファエル・ゲーラ

日墨交流が生んだ「小さな星」
我が国を代表するヴァイオリニスト、黒沼ユリ子さんはメキシコで長年音楽教育活動に情熱を注いでおられることでもよく知られる。昨年1月、彼女が主催するアカデミア・ユリコ・クロヌマの教え子たちが来日して「メキシコ音楽祭」を開いた。これはそもそも日墨修好400年を記念しておととしの5月に予定されていたものだったが、新型インフルエンザ騒動の影響で延期になったものである。残念ながら僕はこの時の演奏会には行けなかったが、その際の来日メンバーの1人、ヴァイオリンのアドリアン・ユストゥスが今回は単独でリサイタルを開くという。これぞリベンジの絶好のチャンスである。7割程度の入り。
最初の曲を書いたシェリングは、あの名ヴァイオリニスト、ヘンリク・シェリングのことである。彼もまたメキシコと縁が深く、第2次世界大戦中にメキシコへ渡り、1946年に市民権を得たそうだ。没後はメキシコで彼の名前を冠したコンクールが開かれ、ユストゥスが第1回で金メダルを受賞したのだそうだ。バッハ風の平均律を思わせる前奏曲を奔放と言っていいくらい伸び伸びと弾く。
「クロイツェル」第1楽章、序奏をじっくり響かせた後第1主題は19小節目のsfをほとんど入れずにpから始め、27で一段落つくまで、少しずつ花が開くような雰囲気を弓の動きと音楽の流れの両方で示す。61〜63の4つの重音も3つ目を少し小さくして4つ目を強く聴かせる。91以降の長い音符が続く部分ではテンポも少し落としてたっぷり歌う。155以降の8分音符には続く長い音符への向けて粘るようなアクセントを付ける。弾き終わると早くも拍手。
第2楽章も落ち着いたテンポで始まる。第1変奏などヴァイオリンの出番が少ないのでつい聞き流してしまうのだが、Cを3つまたは4つ並べただけのフレーズを一つとして同じように弾かない。短調になる第3変奏でさらに少しテンポを落としてゆったりと歌う。
第3楽章は一転して明るくきびきびとした流れで進む。58〜61にかけてバイクがエンジンをふかし直すようなsfを連発し、さらに快調に進む。しかし127〜147にかけては少しテンポを落として丁寧に響かせる。アメリカのJの付いた音楽院出のヴァイオリニストからはとても想像できないような、多彩な音楽風景が次々と繰り出される。見事な表現力である。
この大曲の後でさらにイザイを取り上げるとは、スタミナもただ者ではない。安定した超絶技巧の合い間に「怒りの日」のテーマをくっきり、しかしどこか柔らかさを伴いながら浮かび上がらせる。
「ポンセ」と聞くと僕なんかはすぐ大洋ホエールズの「スーパーカー・トリオ」を思い出してしまうのだが、マヌエル・マリア・ポンセ(1882〜1948)は20世紀前半を代表するメキシコの作曲家。「ソナタ・ブレーヴェ」は「短いソナタ」という意味だそうだ。第1楽章、滝のしぶきを浴びているような爽やかな音楽。第2楽章、夕暮れの表情が目に浮かぶ。そして第3楽章は陽気に踊る。リズム感が鋭くなり、音色も含め前半とは別の楽器を弾いているような感じ。
パガニーニが始まると再びヴァイオリンの世界に戻る。技巧のキレがますます冴える一方で、フレーズの変わり目や結びではテンポを落として大事に弾く。どの曲も聴き応え十分。ほぼ1曲終わるごとに拍手が入る。
「ラ・カンパネラ」では鐘のテーマをあえてレガートで弾くところがユニーク。細かいパッセージをひけらかすよりこの曲に秘められた歌心の方を前面に。
アンコールでは、まずポンセの代表作「エストレリータ」を聴かせ、続いて「サパテアータ」の紹介で足を踏み鳴らす。さらに続いて始まった「スラブ舞曲」はいくら何でもテンポが速過ぎる。と思っていたら、曲が進むにつれてだんだんゆっくりになり、最後は夢の中に消えていくように終わる。お見事!
弓を上げ下ろししながら身体を後方や下手側に回転させるなど大胆な動きを見せることもあるが、艶やかな音色と確かなテクニック、そして何より誰が聴いても彼の音楽とわかる個性がすばらしい。ピアノのゲーラも蓋を全開し、豊かな音量と巧みな節回しで彼を支える。
今のクラシック音楽界では彼のようなヴァイオリニストは目立たないのかもしれないが、だからこそこれからの活躍を大いに期待し、見守っていきたい。
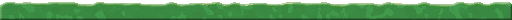
表紙に戻る