 ジョルジュ・プレートル指揮ウィーン・フィル
ジョルジュ・プレートル指揮ウィーン・フィル
○2010年11月10日(水)19:00~21:05
○サントリーホール
○2階LA5列1番(2階下手サイド最後列最奥)
○シューベルト「交響曲第2番変ロ長調」D.125(約27分)(第1,4楽章提示部繰り返しなし、第2楽章・第3楽章主部・トリオ繰り返し実施)
(14-12-10-8-6)
ベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調」Op55(英雄)(約47分)(第1楽章提示部繰り返しなし、第3楽章主部・トリオ・第4楽章繰り返し実施)
(16-14-12-10-7)(コンマス=ライナー・キュッヘル、Va=トビアス・レア、Vc=フランツ・バルトロメイ、Cb=ヘルベルト・マイア、Fl=ディーター・フルリー、Ob=クレメンス・ホラーク、Cl=エルンスト・オッテンザマー、Fg=ステパン・トゥルノフスキー、Hr=トーマス・イェブストル、Tp=マルティン・ミュールフェルナー)
+ブラームス「ハンガリー舞曲第1番ト短調」、J.シュトラウス2世「トリッチ・トラッチ・ポルカ」

老指揮者は死なず、ただ棒振るのみ
当初予定の指揮者がキャンセルした結果とは言え、86歳のプレートルが来日してウィーン・フィルを振る、なんてなことを誰が予想できただろうか?早くも今シーズン最高のサプライズと言っていいだろう。昨日に続きほぼ満席の入り。
シューベルトとベートーヴェンの交響曲しか演奏しないはずなのに、ステージ上には大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングルが用意されている。
プレートルは文字通り颯爽と登場し、指揮台の前で軽やかに1回転してからお辞儀。何と暗譜!シューベルトの2番なんて振ったことあるのかしらん?などと不謹慎な疑問が頭をよぎる。しかし彼が勢いよく棒を振り下ろすと、第1楽章冒頭の和音で背筋が伸ばされ、続く弦の下降フレーズで肩の力が抜けていく。これだけで完全に彼の世界に引きこまれてしまった。こうなると、もう彼は必要最低限の指示しかしない。たとえはよくないが、騎手が走り始めの時だけ一発鞭を入れて、あとは馬なりに走らせているみたい。テンポはほぼ標準的。16小節以降の第1主題も軽快に流れていく。59以降1VとVaが交代で同じフレーズを弾いていく場面でも、彼はそれぞれのパートの方を向くだけ。団員たちは、細かい音符を弾いている時でも昨日に比べてずっとリラックスした表情。ただ、終盤548~549のClのフレーズを浮き立たせるなど、オーストリア系の指揮者では考えられない味付けも時折顔を出す。
第2楽章、棒をヴィオラ奏者の前の譜面台に差して両手で振る。いや、ほとんど振らない。各変奏ごとに「こんな感じでやってね」と言わんばかりに手で形を作るだけ。唯一の例外はハ短調になる第4変奏。ここだけは最初の1小節だけ力強く振る。しかし後はオケに向かって「気を抜くなよ」とばかりに睨みつけるだけ。80の後半でVa以下にクレッシェンドをかける時も彼らの方を向くだけ。
第3楽章、再び棒を持って今度は力強く振る。しかし16~20にかけてはワルツを踊るように腰を振る。トリオでは木管に自由に歌わせる。
第4楽章、最初のうちは頻繁に登場する「タンタタ」の音型に合わせて棒を小刻みに動かしながら振るが、やがてまたオケに任せる場面が増える。シャンペンの泡がグラスの底から浮き上がり、水面に達してはじけて消えてゆく。そんな様子をぼーっと観ているような気分。美しい中にもどこか儚さを感じさせる。
「英雄」第1楽章、雷鳴のように鋭く冒頭の2発を鳴らした後、やや落ち着いたテンポでVcのメロディを弾かせ始める。全奏になる37以降少しずつテンポを上げるが、83以降少し落とし、特に木管を丁寧に響かせる。かと思うと、128以降の6連発はかなり無造作に鳴らす。展開部に入って間もなくの167で1Vのsfを強調。確かに楽譜に書いてあるが、少し大げさにやらせる。だんだん盛り上がって不協和音の連発となる最後の279でなぜかディミニエンド。その後の弦の連続和音は分厚く響かせる。322以降のClとFgのフレーズでかなりテンポを落としてたっぷり歌わせる。338以降徐々にテンポを上げていく。再現部に入って520~521のティンパニは今日も控え目。終盤655以降のTpのファンファーレは堂々と鳴らすが、F-As-B-Bの1つ目のBが少し乱れる。楽章を閉じる689以降の3つの和音では、両手を膝のあたりで左右に激しく振る。
第2楽章、やはり棒は使わない。速めのテンポ。8以降のObソロも少し窮屈そう。なのに56からぐんとテンポを上げる。ハ長調に転じる69以降少し落ち着く。フーガに入って117以降、2Vに向かって「1Vの主旋律に負けるな」とばかりに大きく振る。135以降のHrは堂々たる響き。このあたりまで元気だったプレートルだが、その後だんだん動きが少なくなり、160以降のTpのファンファーレでとどめを刺される。最初の主題が戻ってくる173以降はうなだれて両手をだらんと垂らしたまま。しばらくして復活するが、動きは控え目。ただ、最後の音を鳴らす間右手を軽く握って頭上にかざし、何かを天に向かって放つようにして楽章を閉じる。
第3楽章、ほぼ標準的テンポ。ここでも最小限の動きで軽快に進める。トリオ206以降の木管のアンサンブルが柔らかい。終盤の431以降徐々にテンポを上げて畳みかける。
第4楽章、速めのテンポ。8~10の和音を鋭く鳴らし、11のフェルマータは短め。16以降大きく弾かせる。第2変奏が終わる75で「第1幕終了」とばかりに間を入れる。117以降のフーガでは「対位法なんて関心ないね」とばかりにほとんど指示を出さない。199以降は低音をしっかり鳴らすよう腰で指示。266以降は再びオケに任せる。380以降のHrのメロディも聴き応え十分。431以降オケに最後の鞭を入れ、461以降「多少休符の長さが揃わなくても構わん」とばかりに畳みかける。
プレートルは演奏が終わって台からドスンと降りる時以外、とても年齢を感じさせない。「ハンガリー舞曲」では「プレートル節」全開、「トリッチ・トラッチ・ポルカ」ではニューイヤー・コンサートの華やかさを客席にまき散らす。団員退場後も拍手が止まず、2回呼び出される。
オケを統率するために最低限のエネルギーしか使わないが、しばしばいたずらを仕掛けるように団員たちの思いもつかないような表現を散りばめる。元々老巨匠の好きな日本のクラシック・ファンにとっては、今までにないタイプである。しかも、これまでの老巨匠の日本公演ではみな「これが最後かもしれない」といった悲壮感を持って聴く場合が多かったが、彼の場合年齢的には最後の来日と考えるのが当たり前なのに、あまりに元気がいいので、もう次回のことを想像してしまう。そんな根拠のない希望を抱かせてくれる指揮者は彼が初めてだろう。
マエストロ、すばらしい演奏をありがとう。また来て下さいね。
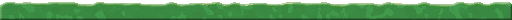
表紙に戻る