 フランツ・ウェルサー・メスト指揮ウィーン・フィル
フランツ・ウェルサー・メスト指揮ウィーン・フィル
○2010年11月9日(火)19:00〜20:50
○サントリーホール
○2階P6列16番(2階舞台最後方から2列目、中央やや上手寄り)
○ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」より「前奏曲と愛の死」(約16分)
ブルックナー「交響曲第9番ニ短調」(約57分)
(16-14-12-10-7)(コンマス=ライナー・キュッヘル、Va=トビアス・レア、Vc=フランツ・バルトロメイ、Cb=ヘルベルト・マイア、Fl=ディーター・フルリー、Ob=クレメンス・ホラーク、Cl=エルンスト・オッテンザマー、Fg=ヴォルフガング・コブリッツ、Hr=ロナルド・ヤネシッツ、Tp=ハンス・ペーター・シュー、Tb=ディートマル・キューブルベック)

不安定で不揃いでもええねん
今年のウィーン・フィル日本公演は、当初小澤征爾との最終決戦といった意味合いを持っていた。しかし小澤は病気のためキャンセルし、代わってアンドリス・ネルソンスとエサ=ペッカ・サロネンが分担して振ることになった。いわゆるオタクたちは当然若手のネルソンスよりも、おととしのロサンゼルス・フィルとのコンビで評価を高めたサロネンの指揮ぶりに注目した。しかしサロネンもキャンセルしてしまった。そこで、サロネンが振る予定の演奏会は、今月後半元々クリーヴランド管と来日する予定だったフランツ・ウェルザー=メストと、86歳のジョルジュ・プレートルが分担することとなった。異例の事態への対応にホール側も大変だったと思うが、結果としてこれまでにない豪華な顔触れが揃うこととなった。ほぼ満席の入り。
団員達の席が指揮台に向かってかなり詰めて配置され、ステージの後ろはがらんとしている。最後列の配置がユニークで、下手側からティンパニ−Tp−Tb−Tu−Hr−Cbの順。チューバが指揮者の真正面に座る。
「トリスタン」冒頭のVcのメロディが天上から降ってくる。これぞウィーン・フィルの響き。メストも一瞬これに酔ったか、前半は彼にしては落ち着いたテンポで進めるが、中盤で木管がメロディを奏で終わるあたりから徐々にテンポを上げ、Vがメロディを力強く弾き始めるところでさらにテンポを上げる。クライマックスに達してもそのままのテンポで走り、その波が去ったところでようやく少しテンポを落とす。「愛の死」でも途中で2段階に分けてギアチェンジをするようにテンポを上げていく。終盤の頂点を過ぎてもほとんどテンポは落ちず、Obだけが残る最後の和音の切れ目もほとんど聴かせず、続く大きな波にも溺れることなく短めに切って終わる。
ブルックナーの9番第1楽章、この曲の壮大さを感じさせないようなさりげない弱音から始まる。速めのテンポで63小節の最初の頂点まで淡々と進む。第2主題が始まる97以降もかなり速い。団員に音楽に酔うのを禁じたかのようだ。しかし、115以降のVaとCbは厚く響かせる。145〜146のVのアクセントは丁寧に柔らかく付ける。276のフェルマータ付全休止は短め。325以降スコア通りアッチェランドをかけるが、かなり強烈。333以降の弦の激しい動きはジェットコースター並み。それが一旦収まる355以降もほとんどテンポを落とさず、380以降の頂点まで一気に突き進む。第2主題が戻ってくる421以降もテンポを落とさない。503〜504のHrパートソロから505以降の木管合奏への受け渡しでも間を取らない。その後も速いテンポのまま進み、548冒頭の全奏の後に残る管楽器の3連符2拍に覆い被さるように全奏のユニゾンが続く。551以降は堂々たる音の伽藍が完成。最後の音は弦がしっかり延ばしてから閉じる。
第2楽章、少し落ち着いたテンポ。序奏に続く42以降の第1主題、重くて分厚いDのユニゾンに圧倒される。ここではさすがに前へ進むよりも一音一音しっかり鳴らすことを重視しているようだ。しかし、中間部から第1主題へ戻っていく147以降からどんどんテンポが上がっていき、回転しながら墜ちていくセスナ機に乗ったような気分。
トリオも速めのテンポで進んでいったのだが、終盤の231〜232の1Vの上昇音型で全員が出られず、すかさずもう1回繰り返して次のフレーズへ。これだけなら大半の聴衆は気付かなかったと思うが、主部に戻った序奏の冒頭でObだけしか出られず、またも間髪入れずObとClが最初からやり直す。スリル満点。ただ、これにも気付かなかった聴衆は多いかも。
第3楽章、テンポはやはり速いが、メストが1Vの方を向いて、一音一音確認するようにしながら冒頭の主題を弾かせる。7〜8のVcとCbのフレーズもしっかり地に足の付いた響き。17以降の全奏も迫力十分。29以降の4本のワーグナー・チューバの響きが暗くて渋くて実にいい。45以降のVの第2主題も力強く歌う。105以降121に至るまでの長いクレッシェンドでも緊張感を持続。171〜172のObとClの8分音符の連打の後は間を入れずに次のフレーズへ。187以降も息長く着実に盛り上げていき、199以降再び音の伽藍が出現するが、206の最後の不協和音は短めに切る。その後は淡々と進み、239以降最後の和音のワーグナー・チューバの音程がやや不安定だったが何とか持ちこたえる。
メストが振るのはこの日1回だけで、リハーサルの時間も短かったようだ。ウィーン・フィルはこれまでに何回も振ってはいるが、団員たちと気心知れる関係にまではまだまだ至ってないだろう。弦の響きは全体的に骨太だったし、ウィーン・フィルらしからぬアクシデントも起きたし、速いテンポでどんどん進む彼のスタイルはベテラン団員と若手団員との間でも受け止め方が違うようだ。特にヴァイオリン・パートでは、スコア通りに弾く者と速いテンポなりにためを作って弾く者とのずれがしばしば表面化していた。また、ティンパニの存在感が薄いのも気になる。
しかし、今はこれでいいのだ。思わぬ形とは言え、拙著「かなり変だぞ クラシック通」で私が待望していたメストとウィーン・フィルの組合せが日本でもようやく実現したのだから。ウィーン・フィルの新しい歴史はここから始まるのだと信じたい。
最後に、2曲とも指揮者が棒を下すまで拍手を控えた聴衆にブラヴォー!
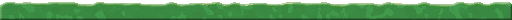
表紙に戻る