 グスターボ・ドゥダメル指揮シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オヴ・ベネズエラ(3回公演の2回目)
グスターボ・ドゥダメル指揮シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オヴ・ベネズエラ(3回公演の2回目)
○2008年12月18日(木) 19:00〜21:35
○東京国際フォーラム ホールA
○2階26列76番(2階最後列上手)
○ベートーヴェン「三重協奏曲ハ長調」Op56(約38分)(14-12-10-8-6)
P=アルゲリッチ、V=ルノー・カプソン、Vc=ゴーティエ・カプソン
+同第3楽章332小節以降
マーラー「交響曲第1番ニ長調」(巨人)(約55分、繰り返し全て実施)
(28-23-19-21-12)
(下手から1V-2V-Va-Vc、CbはVcの後方)
+バーンスタイン「ウェストサイド物語」より「マンボ」

奔放と規律の見事な融合
NHKがドキュメンタリー番組を放送して以来日本でもすっかり有名になったシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オヴ・ベネズエラ(SBYO)。その来日公演がこの年の瀬に実現するというわけで、忘年会の合い間を縫って駆け付ける。何で5000席のホールでやるのよ!?などとぜいたくは言っていられない。1階席は8割程度埋まっていたようだが、2階席は半分程度の入り。
開演ベルが鳴り、団員たちが入ってくる。男性は黒の上下に白のYシャツと黒ネクタイ、女声も服のタイプはいろいろだが色は黒で統一。それにしても入場の仕方がバラバラで、下手側が揃っても上手のコントラバスとチェロの一部はまだ入ってこない。このあたりはいかにもラテンアメリカらしい。コントラバス奏者の大半は立って演奏。
前半はアルゲリッチ、カプソン兄弟との夢の共演。ソリストは全員譜面を見ながら演奏。第1楽章冒頭の低弦の主題、レガートだがややおとなしい感じ。テンポはほぼ標準的。しかし59小節以降弦は付点のリズムや重音のスタッカートを版で押したようにきっちり刻んでゆく。77以降のチェロのソロ、楽譜通りdolceで優しく始める。85以降のヴァイオリンもこれに続き、90以降の二重奏も息がぴったり。これに対し97以降のピアノはマイペースだが全体のアンサンブルから飛び出るほどではない。前半のクライマックスになるソロ3人のトリル(223〜224)でアルゲリッチが他の2人より一瞬早く切ってしまうところは相変わらず。315以降3人が次々と上昇音階を弾いて盛り上げる所でも、特にヴァイオリンとピアノがうまく興奮を高めてゆく。
第2楽章、弦が冒頭主題をレガートできれいに響かせる。4以降のチェロのソロがこの雰囲気をしっかり受け継ぐ。細かい音符の多いピアノもここは終始弱音で通す。第3楽章へつながる53のチェロのクレッシェンドがやや不十分だが、第3楽章に入るとまたも柔らかい歌で全体をリードする。ここでもぴったり寄り添うヴァイオリンとチェロに対し、ピアノがしばしば自分のペースに引き込もうとするが、カプソン兄弟は冷静に対応。しかし、終盤の332以降はテンポをぐんと上げ、3人とも一気に駆け出す。オケも396以降は爆発し、444,446などの全奏をしっかり決めるなどして盛り上げる。473〜475の最後の3つの音、アルゲリッチはペダルを踏みっぱなしにするので休符の間もピアノの余韻だけ残る。
ソリスト3人と指揮者はときどき歓談?しながらゆっくり出入りを繰り返す。そして、第3楽章終盤をアンコールで演奏という大サービス。ただ、カーテンコールの間1人しつこくブーイングする者あり。アルゲリッチへの不満か?確かにすっかりおばあさんになっちゃったし、柔らかい音色で緊密なアンサンブルを創り上げるカプソン兄弟に多少遠慮している感じはしたが、しばしば速いフレーズで切れ味のいいところを聴かせた。
後半の弦の人数は冗談ではありません。第1Vは第1列が8プルト、第2列が6プルト、チェロは何と6列で並んでいる。2つのオケの合同演奏会でもない限り、これだけたくさんの弦楽器奏者がステージに並ぶのを見ることはない。それでもステージにはまだスペースの余裕があるが、100人を越える弦が5000席のホールをどれだけ鳴らすことができるか、俄然面白くなってきた。
「巨人」第1楽章、冒頭の弦は楽譜の指示通りpppだがはっきり聴き取れる程度の音量。62以降の低弦の第1主題は控え目な弾きぶりで、むしろ64から加わるバス・クラリネットの方がしっかり自己主張している。テンポは速め。143以降弦全体がfで鳴り出すとさすがに響きに厚みが出てくる。316以降延々と続くVなどの急激な<>や344〜347のVa以下のタンタタの刻みも、過激ではないがきちんと聴こえる。352以降金管が鳴っても弦が負けていない。前半Hrがやや不安定だったが、気にしない。
第2楽章、最初の4小節の低弦を特にゆっくり、もったいぶりながら弾かせる。しかしその後はすぐ速めのテンポに。37でVのHを強調し、一瞬間を取って次のEへ。108以降の低弦の刻みも明確。166〜167の管楽器のトリルもおとなしめ。トリオが終わって主部に戻る285以降は1回目のようにテンポを落とさない。しかし、317のVには37と同じ表情を付ける。
第3楽章、コントラバスのソロも安定している。ここもテンポは速め。22〜23のObの下降フレーズ、GとFにスタッカートを付けずレガートで吹く。全体的に薄味であまり極端な歌わせ方はしない。ただ打楽器が加わる56〜60はややノリがよくなる。
第4楽章、速めのテンポ。弦がエンジン全開で真っ向から管楽器・打楽器に対抗。54以降第1V、第2Vをはっきり聴き分けることができる。他方143以降の管楽器の急速な<の繰り返しはあっさり通り過ぎる。175以降の弦の息長い歌も意外と淡白。ただし、頂点の218でVとVaのFのフェルマータの後一呼吸置いて次のフレーズを弾く。しかし、254以降は再びVとVa以下の弦が管・打楽器とがっぷり四つに。なかなか快感。第1楽章冒頭の序奏に戻った後の430以降のHrのアンサンブルは見事。終盤になっても弦の響きは衰えず630以降もTpのファンファーレなどにしっかり絡む。686からさらにテンポを上げ、一気にゴールを駆け抜ける。
客席にはベネズエラの国旗を持った青年たちが熱狂してステージに向かって振り続けている。そのうち陸上競技のウィニング・ランみたいに国旗を掲げて通路を走り出す者も。
何回かカーテンコールがあった後突如舞台は暗転。しばらくして再び明るくなった舞台にはベネズエラの国旗模様のトレーナーに着替えた団員たち。さらに拍手喝采。ただ、何人か楽屋に忘れてきたのか、Yシャツにネクタイ姿の者がいる。このあたりの不徹底ぶりがこれまたラテンアメリカらしい。「マンボ」ではチェロやコントラバス奏者たちが楽器をくるくる回し、ヴァイオリン奏者たちは立って踊りながら弾くという得意のパフォーマンスも披露。もちろん聴衆は大喜び、みな拍手し続けているが、最後は団員たちがトレーナーを脱いで客席に投げ始めたから1階席前方に人が殺到。2階席の客たちは帰り始め、これで拍手は自然消滅。何とも締まりのない終わり方がこれまたラテンアメリカらしい。
ステージでの奔放な行動とは裏腹に、演奏自体は確かに若いエネルギーのほとばしりは感じるものの、それ以上に強く印象に残ったのは、全ての団員たちが基本に忠実な奏法をきちんと守っているという点である。だからしばしば情熱を表に出し過ぎてアンサンブルがバラバラになる他のユース・オケに比べ、はるかに規律正しく水準の高い演奏ができている。これには驚いた。もちろんドゥダメルのリーダーシップに負うところもあろうが、これこそ「エル・システマ」の真髄なのだと悟る。
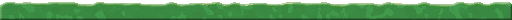
表紙に戻る