 ラトル指揮ベルリン・フィル(6回公演の3回目)
ラトル指揮ベルリン・フィル(6回公演の3回目)
○2008年11月26日(水) 19:00〜
○サントリーホール
○2階P2列33番(2階ステージ後方2列目下手端)
○ブラームス「交響曲第3番ヘ長調」Op90(約40分、第1楽章提示部繰り返し)
(同「同第4番ホ短調」Op98)
(16-14-12-10-8)(下手から1V-Va-Vc-2V、Cbは2Vの後方)
(首席奏者:コンマス=スタブラヴァ、第2V=ティム、Va=レーザ、Vc=ファウスト、Cb=シュトール、Fl=ブラウ、Ob=ウィットマン、Cl=フックス、Fg=シュヴァイゲルト、Hr=ドール、Tp=ヴェレンチャイ、Tb=オット、ティンパニ=ゼーガース)

仲良しクラブで終わりませぬように
この日も当然ながらほぼ満席の入り。今日は安永さんは次席。清水さんは今日もヴィオラの次席。
ブラ3第1楽章、やや遅めのテンポ。この曲をカラヤンはいつも快速テンポで押し通していたので、何だかほっとする。6小節目VのE−Dの音型でpに落とす。38でClは楽譜通りppに落とす。50以降はVcの上昇音型の繰り返しを意識させながら振る。183から少しテンポを上げ、188以降の弦は休符をほとんど取らずに前のめり気味に進んでゆく。194以降も同様。206以降は1Vと交互に出てくるVcの音型(G−FEなど)を歌わせる。
第2楽章、ほぼ標準的テンポ。Clが冒頭の主題を繰り返す5以降ppに落とす。44のClとFgも前の小節の>を守ってppに落とす。63以降のVaもゆったり歌わせる。盛り上がった頂点の80のVもレガートでほとんどスタッカートをかけない。108以降テンポを少し落とし、弦を丁寧に歌わせてゆく。あまりの美しさに聴き惚れる。
第3楽章、ほぼ標準的テンポ。24以降も楽譜通りppに落とす。ここでもスムーズに流れるが、泣きはあまり入らない。中間部の57でメロディがFlからClに受け継がれるとまたppに落とす。74のfも抑え気味。主部に戻って98以降のHrソロがこれまたpppくらいで吹き通し、絶品。156以降最後の盛り上がりもあまり大げさにならない程度で収める。
第4楽章、やや遅め。fになる29以降弦のスタッカートは控えめ。44で一旦pに落としてから<をかける。91以降のsfの連続も控えめ。134以降の弦のマルカートもあまりかけずレガートを維持。全奏は力強く進むが、第1楽章終盤のようにあおる場面はない。長調に変わる267以降は自然に興奮が鎮まってゆく感じ。
第2〜4楽章は続けて演奏。座席の位置の関係で第3Hrがよく聴こえたが、全体的には昨夜も含めて弦、管とも最も一体感のある演奏だったのではないかと思う。
ブラ4は残念ながら、諸般の事情により聴けませんでした。
2日目は残念ながら半分しか聴けなかったわけだが、一応2日まとめての感想を書いておきたい。
カラヤン時代を知らない若い聴衆が昨夜やこの日の演奏を聴いて感激するのは無理もない。しかし、僕より上の世代はカラヤン時代のベルリン・フィルと比べてどうだったか、コメントする責務がある。
カラヤンの振るベルリン・フィルはとにかく全ての面で圧倒的だった。特に88年最後の来日公演は、このコンビがサントリー・ホールで演奏する結果的に唯一の機会でもあったのだが、衰えたりとは言えカラヤンはオケに対してにらみを利かせ、団員たちはこれに必死で食らいつく。分厚く響く弦、高らかに鳴り渡る管は文字通りホール中を轟かせ、津波のような音楽が聴衆を飲み込んだのであった。
あれから20年後の今年の来日公演、ラトルは終始にこやかな表情でオケに接し、3分の1から半分くらいは振らずにオケが演奏するに任せている。団員たちも終始リラックスした表情で弾いている。オケの響きは室内楽的でどのパートも一分の隙なくがっちりかみ合っているが、その響きはステージの上でだけまとまっており、ホール全体が鳴り響く場面はほとんどない(特に1番)。美しさに聴き惚れる場面は何度もあったが、圧倒されるまでには至らなかった。
指揮者と言えど絶対君主のようにオケを支配することは許されない時代になっているのはわかる。しかし、それは運営面の話であって、演奏面で信頼関係に基づく民主的な手法がよりよい結果につながるかどうかはわからない。ステージ上でラトルとベルリン・フィルが仲良く演奏しているのを見るにつけ、彼らの蜜月関係が今後音楽上の緩みにつながらないよう祈りたくなるのは、僕だけではあるまい。
また、ラトルの解釈はもう一つの意味での「民主化」を進めている。彼が力を入れて振ったり指示したりするのは、大半の場合伴奏パートかリズムを刻むパートである。おかげで主旋律を奏でるパートとそれ以外のパートとの間の音量差は小さくなり、楽譜上に書かれた全ての音楽が渾然一体となって聴衆に示される。
この解釈は室内楽的なオケの響きと確かに合致している、いや、むしろこの解釈のためにオケの響きも変化してきたと考えるべきだろう。しかし、カラヤンの演奏を知る者としては、メロディと伴奏の区別を明確にした彼の解釈が懐かしく思えてしまう。いや、これは単なる懐古趣味ではない。今回の演奏を聴く限り、ラトルのアプローチはカラヤンと異なる解釈として十分説得力があるようには思えないのである。
このコンビの演奏は今後どのように成熟し、あるいはさらに変化してゆくのか?引き続き目が離せないことだけは確かである。
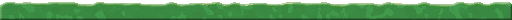
表紙に戻る