 フェスティバル・ソロイスツ with レオン・フライシャー(P)
フェスティバル・ソロイスツ with レオン・フライシャー(P)
○2008年5月15日(木) 19:00〜21:10
○サントリーホール
○2階LD2列2番(2階下手奥2列目端から2席目)
○バッハ「フーガの技法」BWV1080より第1番、第19番、コラール前奏曲「われら悩みの極みにありて」(BWV668a)
ベートーヴェン「セレナードニ長調」Op7(約33分)(繰り返し全て実施)
ブラームス「ピアノ五重奏曲へ短調」Op34(約45分)(繰り返し全て実施)
○V=竹澤恭子、長原幸太(バッハ、ブラームス)、Va=豊嶋泰嗣、Vc=堤剛、P=フライシャー(ブラームスのみ)

室内楽の難しさを再認識
室内楽のコンサートへ行くのはいつ以来だろうか?好きなのだがなかなか予定が合わない。しかし、フライシャーが日本の第一線の演奏家たちと共演するとなれば話は別。サントリーの大ホールだと広過ぎるのではないか?などとぜいたくを言っている場合ではない。Pブロックを閉鎖していたが、それでも7割程度の入り。
最初に弦楽四重奏によるバッハ。「フーガの技法」からの抜粋とは言え、腕慣らしとはとても言えないプログラム。速めのテンポで生真面目に、文字通り積み木を重ねるように進んでいく。19番は楽譜通り中断。それまでの音の建築が立派なだけに唐突な感じが増している。その穴埋めとして作られたコラール前奏曲は心の整理が付かない聴衆を静めるような雰囲気ではあるが、調性(ト長調)がフーガの主題(ニ短調)と関係ないので、どこか違和感が残る(そんな風に感じるのは僕みたいなひねくれ者だけかも)。
ベートーヴェンは竹澤、豊嶋、堤による演奏。僕は、ベートーヴェンが若い頃貴族のサロン・コンサート用に書いたこのような作品が苦手である。親しみやすいメロディがたくさん現れる割には素直に楽しめない。「オレはこんな音楽を書くために生まれてきたんじゃない」みたいな不満が奥に潜んでいるように感じるからである。
この日の演奏にも理由の一端があった。強靭な音だがあまり伸びやかに歌わない竹澤のヴァイオリン、独自の境地に達した堤のチェロ、その2人の橋渡しに苦慮する豊嶋のヴィオラ、といった感じで、どうも聴いていて落ち着かない。ただその中では第5楽章の変奏曲が一番よくまとまっていたと思う。
それにしてもこの夜の聴衆はいつもと少し違う。バッハの1曲目、ベートーヴェンの3,4楽章の後に拍手が起こる。
ブラームスについてはこちらをご覧下さい。
一流の演奏家を集めればいい室内楽ができるかと言えば、そう簡単にはいかない(どこかの球団の話みたいだが)。演奏家同士の個性がぶつかり合うだけでもダメだし、妥協して各人の持ち味を引っ込めても面白くない。そんな室内楽の難しさを再認識。だからもっと聴きに行きたい。
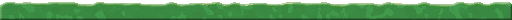
表紙に戻る