 トビリシ弦楽四重奏団(V=ギオルギ・バブアゼ、チプリアン・マリネスク、Va=ザザ・ゴグア、Vc=ギア・ケオシヴィリ)&田隅靖子(P)「グルジアの響き」
トビリシ弦楽四重奏団(V=ギオルギ・バブアゼ、チプリアン・マリネスク、Va=ザザ・ゴグア、Vc=ギア・ケオシヴィリ)&田隅靖子(P)「グルジアの響き」
○2008年2月9日(土) 14:00〜16:15
○東京文化会館小ホール
○Q列32番(17列目ほぼ中央)
○ヴァジャ・アザラシヴィリ「祖国グルジアの風景」より「イメルリ」「あなただけに」「ラブ・ソング」「ユーモレスク」「チェラ」
スルハン・ツィンツァゼ「弦楽四重奏のための8つの小品」(「スリコ」「インディミンディ」「チョングリ」「サツェクバオ(舞踏曲)」「ツィンツィカロ(早春)」「ソプルリ(田舎の踊り)」「蛍」「口うるさい女房」)
ヨセフ・バルダナシヴィリ「ピアノ三重奏曲」(ビゼーの思い出に)(V=バブアゼ、Vc=ケオシヴィリ、P=田隅)
オタール・タクタキシヴィリ「ヴァイオリンとピアノのための3つの小品」(V=バブアゼ、P=田隅)
ギア・カンチェリ「弦楽四重奏曲」(夜の祈り)
+ヴァジャ・アザラシヴィリ「ノクターン」(トビリシ弦楽四重奏団、P=田隅)

グルジアがぐんと身近に
またも私事から始まるが、家内のピアノの師匠である田隅靖子さんが昨年11月カワイ表参道でのコンサートに引き続いて東京で演奏をされるというので、とにもかくにも駆けつける。ただ、今回の主役はグルジアの弦楽奏者たちが1998年に結成したトビリシ弦楽四重奏団である。ちなみに、このコンサートを主催する「冬のチェンバロの会」は96年に結成され、大阪や神戸で室内楽を中心にユニークな演奏会を企画・実施している音楽愛好者の集まりだそうだ。
グルジアと言えば旧ソ連解体後に独立し、ゴルバチョフの下で外務大臣を務めていたシェワルナゼが大統領を務めていた、というくらいのイメージしかない。グルジア出身の作曲家なんて誰も知らないし、あとは大相撲の黒海くらいだよなあ、と思っていたら、ちょんまげ結んだ大男が3人ほど会場に入ってくる。あ、ほんまに黒海関や!あと初場所で十両優勝した栃ノ心関もいる!(残る1人は家に帰って調べたら、幕下の臥牙丸(ががまる)と判明。)下手端最前のパイプ椅子に座り、グルジア大使館員らしき人たちと談笑している。8割程度の入り。
アザラシヴィリは36年生まれ、現在も活躍するグルジアを代表する作曲家だそうだ。「イメルリ」はヘ長調で始まる軽快な舞曲が繰り返されるたびに半音ずつ上がっていく。昔のドリフターズのコントを見るみたいで、トビリシ駅ガード下(そんなものがあるかどうか知らんが)で繰り広げられる大道芸が目に浮かぶ。「あなただけに」「ラブ・ソング」は一転して落ち着いたムード。今度は場末の居酒屋に座っている。「ユーモレスク」では再び明るく活発な音楽になるが、「チェラ」では海の見える高級ホテルのバーにいるような雰囲気に。たった5つの小品を聴いただけで、もうグルジア観光をしたような気分になる。
ツィンツァゼ(25〜91)はアザラシヴィリの一世代前の巨匠だそうだ。「スリコ」はカントリー風の調子のいい曲だが、第2ヴァイオリンが弾きながら左手の薬指と小指でピツィカートを混ぜる。「インディミンディ」はドヴォルザークの「スラヴ舞曲」Op46の1を思わせる賑やかな曲。「チョングリ」では第2ヴァイオリンとヴィオラが、窓からもれる透き間風のような音を聴かせる。「サツェクバオ」ではチェロ以外の3人が楽器をギターのように抱えてピツィカートのみで演奏。思わず拍手が起こる。「ソプルリ」は単純なリズムの繰り返しだが、これもどこかスラヴ風の舞曲に似ている。「蛍」では、まだ明るさの残る初夏の宵の草むらで蛍が漂うように飛ぶ感じ。「口うるさい女房」では8分音符と付点4分音符のリズムを多用。あまりにリアルな表現に苦笑。
バルダナシヴィリは48年生まれ。現在はイスラエル在住。「ビゼーの思い出に」は単一楽章の作品。イ短調のピアノソロから静かに始まり、それを後追いするように弦の2人も静かなメロディを奏でるが、しばらくするとピアノが低音を激しく叩く上を弦が攻撃的なメロディを鳴らす。その後ヴァイオリンとチェロがユニゾンで瞑想したかと思うと、遠くでバラバラに歌い始めた3人がだんだん寄り添って輪を作っていったり、3人がトレモロで会話したりする。後半ピアノ・パートには、立って左手で低音の鍵盤を叩き、右手で弦を押えるよう指示された場面がしばしばある。最後はこれに弦の2人が左手で弦を持ったまま胴を叩いて加わり、消え入るように終わる。
タクタキシヴィリ(24〜89)はツィンツァゼと同世代。1曲目(アレグロ・レッジェーロ)はホ短調の平易なメロディで始まるが、展開部になるとそれがどんどん変形され、追い詰められるような緊迫感を生み出す。2曲目(アンダンテ)は闇の中を妖精が行き交うような感じ。3曲目(アレグロ・モルト)はラヴェル「マ・メール・ロワ」の「パゴダの女王レドロネット」を思わせる東洋的な響き。ピアノ・トリオで難曲を弾き切った2人が今度は落ち着いたアンサンブルを聴かせる。
カンチェリは35年生まれ、グルジア国外でも高く評価されている作曲家だそうだ(ちなみに井上和男編著「クラシック音楽作品名辞典 改訂版」(三省堂)に載っているのはツィンツァゼ、タクタキシヴィリ、カンチェリの3人)。全員による不協和音の連続で始まる。ただ最初のうち、チェロだけは左手で弦を指板ごと握った状態で弾くので音がほとんど鳴っていないような感じ。E−FやF−Eなど半音の上昇・下降音型をモザイクのように組み合わせてハーモニーを作っていく。終盤になるとトンネルの奥がゴーッと鳴っているようなテープ音が加わり絶望的な雰囲気になっていくが、やがてソプラノの声(テープ)が加わって救われたような気分になる。
鳴り止まぬ拍手の中ピアノが再び中央に移動、初めて5人全員のアンサンブルが聴ける、と思いきやチェロ奏者がスコアを取りに舞台裏へ戻る。第1ヴァイオリンのバブアゼさんが、とっさの機転で流暢な日本語でお礼の挨拶。思わぬ展開に聴衆も大喜び。グルジアの四重奏団を名乗っているが第2ヴァイオリンはルーマニアの人だと紹介すると、笑いがもれる。ようやくチェロ奏者も戻って始まったアザラシヴィリの「ノクターン」は、杏里「オリヴィアを聴きながら」に似たフレーズが出てくるなど、むせ返るようなロマンチシズムにあふれる曲。暗い中にもほのかな甘さを備えた弦とベーゼンドルファー・インペリアルの豊かな響きとの融合に思わずうっとりと聴き惚れる。
改めて奏者の経歴を見ると全員関西のオケの現役団員または元団員。終演後田隅さんに聞いた話では、ルーマニア出身のマリネスク氏以外は、家族を故国に残したまま10年以上も単身赴任状態なのだそうだ。音楽市場の国際化がもたらす負の側面を垣間見る。ただそのおかげで、グルジアから生み出された多彩な音楽の数々を耳にする機会に恵まれたのも確か。今回はこれを素直に喜ぶこととしよう。
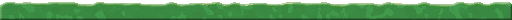
表紙に戻る