 デヴィッド・ロッキントン(David Lockington)指揮ナッシュヴィル交響楽団(3回公演の2回目)
デヴィッド・ロッキントン(David Lockington)指揮ナッシュヴィル交響楽団(3回公演の2回目)
○3月2日(金) 20:00〜22:05(米国中部時間)
○シャーマー・シンフォニー・センター ローラ・ターナー・コンサート・ホール
○バルコニーF列30番(4階中央6列目上手端)
○アドルフス・ヘイルストーク(Adolphus Hailstork)「交響曲第3番」第2,3楽章(13-12-9-10-7)
マーク・オコナー「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」(For the Heroes)(約32分)(13-12-9-10-6)
(V=マーク・オコナー、Vc=マヤ・バイザー(Maya Beiser))
メンデルスゾーン「交響曲第3番イ短調」Op56(スコットランド)(約41分、第1楽章提示部繰り返し)(13-13-9-10-7)
(下手から1V-2V-Va-Vc、CbはVcの後方)

カントリーの聖地の幸福なオーケストラ
ヴァージニア州の南東、テネシー州の中心部に州都ナッシュヴィルがある。人口60万足らずの都市だがカントリー音楽発祥の地として知られ、中心部にあるカントリー音楽殿堂博物館は特に有名である。しかし、昨年9月そのはす向かいに本格的なコンサート・ホールが開場したことはほとんど知られていないだろう。
シャーマーホーン・シンフォニー・センターと呼ばれるギリシャ神殿風建物の中に約1,900席のホールがある。センターの名前は作曲家でナッシュヴィル交響楽団の音楽監督を20年以上務めたケネス・シャーマーホーンにちなんだもの。NSO(ワシントン・ナショナル交響楽団)の音楽監督レナード・スラトキンがもう一つのNSO(Nashville
Symphony Orchestra)の音楽アドバイザーに就任してこのホールの開幕記念コンサートを振り、ちょっとした話題になった。
たまたま仕事でこの街を訪れることになり、日本に帰国する前夜に定期演奏会へ行くことができた。センター右手のボックス・オフィスでチケットを買ってホワイエに入るがもぎりがいない。そのままバルコニーまで上がり客席の入口まで進むとようやく座席案内人が現れ、チケットをちぎる代わりにセンサーでバーコードを読み取る。日本の厳重なチケット・チェックが当たり前の身には何とも拍子抜けの応対である。
ホワイエの壁には大手スポンサーであるサン・トラスト銀行の支援で、鏡のようなディスプレイに今後の演奏会の予定が電光掲示される。その横には全団員の顔写真、氏名、出身地と団員になった年が掲載されている。第2ヴァイオリンに横浜出身のナガヨシケイコさんが2004年から加わっているのがわかる。
客席に入ると薄緑の壁が美しい。シューボックス型で日本ならオペラシティのホールに似ているが、両端のバルコニーの椅子が舞台側に45度傾いて設置されている。7割程度の入り。
ヘイルストークは1941年ニュー・ヨーク生れのアフリカ系。なかなか演奏機会のないアメリカ人作曲家の作品を取り上げるシリーズの一環としてプログラムに組まれている。指揮者と作曲家本人が登場し、簡単な曲目紹介後演奏が始まる。満天の星が輝く夜空のような弦の響きが美しい第2楽章、切れ目なしに続く第3楽章では様々な打楽器が民謡風リズムをしつこく繰り返してゆくが、どこかのどかな雰囲気。全曲聴けないのが何とももったいない。
オコナーはワシントンのNSOでも聴く機会があった(2005年6月17日の批評参照)。彼自身はシアトル生まれだが現在のカントリー音楽界を代表するフィドラー・作曲家であり、ナッシュヴィルのNSOには実にふさわしい。チェロのバイザーはイスラエル出身でフランス人の母とアルゼンチン人の父の間に生れた。黒の燕尾付ドレスで登場。
「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」と言えばブラームスの作品を思い出すが、この曲は9.11同時多発テロの1ヵ月後に書かれ、「英雄のために」(For the Heroes)と題されている。あの悲劇的な出来事の後であっても希望を捨てずに生き続ける人間の気高い精神を表現しようとしている。
第1楽章、序奏なしにいきなりヴァイオリンが元気なメロディを奏で、それをチェロがなぞっていく。互いに相手を刺激しながら曲は進み、オケがしばらく鳴ってもまたすぐ2人の掛け合いに戻る。「ワルツ」と題された軽快な第2楽章を経て、第3楽章でもソロの2人がほとんど休みなく引き続ける。特に中間部のカデンツァではバイザーがスコアを2枚めくってもまだ終わらない。30分を越える大曲だが背景を知らなければ単にノリのいい愉快な音楽として聞き流してしまいそう。
「スコットランド」第1楽章冒頭、チェロより少ないヴィオラをしっかり鳴らす。スコットランドの海岸の岩肌に荒波がぶつかる寂寥とした風景が目に浮かぶ。金管が加わっても飛び出さず、アンサンブルのバランスを保っている。
第2楽章、クラリネットのソロが少々頼りない音で最後の高いCが消え入りそうになる。続くホルンは溌剌とした音。5人中首席を含め4人が女性というところがいかにもアメリカのオケらしい。
第3楽章でも弦のメロディを丁寧に歌わせ、枯れ草に覆われた野原にときどき薄日が差し込む様子が目に浮かぶ。終盤では夕日がゆっくり沈むような感じ。
ここまでなかなかいい雰囲気だったが、第4楽章に入ってから弦の細かいフレーズなどにところどころほころびが見え始める。少しテンポが上がると言うより気ぜわしい感じになる。長調に転じると意外に大きな音量で始まり、そのままゴールに突入。
弦は大都市のオケに比べて人数こそ少ないものの響きの厚みに問題はなく、むしろコントラバスの支えはしっかりしている。ただ、ホルン以外の管楽器がおとなしいのはアメリカのオケらしくない。
ロッキントンはイギリス出身だが指揮を学んだのはイェール大学で、活動の大半はアメリカやカナダのオケを率いてのものである。
驚いたのは聴衆の反応。オコナーでもメンデルスゾーンでもカーテンコールは1回のみであっさり拍手が止んでしまう。別に演奏に不満があるわけではなく、立って拍手したりブラヴォーをかけたりする者もいるにはいる。聴衆のほとんどが高齢者であることを考えてもあまりに淡白である。
このような反応と指揮者・オケの演奏ぶりとの間に関係があるのか否かは、この夜の演奏会を聴いただけではわからない。ただ、こんな立派なホールでクラシックの定期だけでも13プログラム、しかも同じプログラムを3回演奏する。他に演奏会形式のオペラや「メサイア」などの特別コンサート、そしてポップスのプログラムを合わせると今シーズンの演奏回数はちょうど100回に達する。
日本の地方都市でこのようなぜいたくな規模のシーズン・プログラムを組めるオケがないことを考えると、改めてこの国の豊かさとそのことを当たり前に感じる聴衆の能天気さを思わずにはいられない。その象徴があの拍手の淡白さに現れているように感じるのはうがち過ぎだろうか?
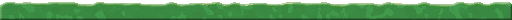
表紙に戻る