 ワシントン・ナショナル交響楽団定期演奏会(3回公演の初日)
ワシントン・ナショナル交響楽団定期演奏会(3回公演の初日)
○V=ニコライ・スナイダー、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ指揮ワシントン・ナショナル交響楽団
○5月6日(木) 19:00〜21:05
○ケネディ・センター・コンサート・ホール(米国ワシントンDC)
○Chorister
A-102(舞台後方最前列下手端から2席目)
○オーガスタ・リード・トーマス「銀河の踊り」(Galaxy
Dances)(世界初演)(16-16-9-12-8)
グラズノフ「ヴァイオリン協奏曲イ短調」(15-15-9-11-7)
ショスタコーヴィチ「交響曲第5番二短調作品47」(16-16-10-12-8)(約46分)
(下手より1V-2V-Vc-Va、Vcの後方にCb)

帰ってきたロシアの農夫
NSOの前音楽監督で桂冠指揮者のロストロポーヴィチが98年以来の登場。奇しくもNBCの長寿ドラマ「フレンズ」がこの夜最終回を迎え、そのせいでもなかろうが会場は8割程度の入り。客層は「フレンズ」をとっくに卒業したと思われる世代が大半かと思ったが、まだちょっと早いと思われる世代も意外に目立つ。
チューニングが終わると、黒のイブニング・ドレスを着た女性が登場。最初の曲の作曲家その人であった。初演前に作曲の経緯や曲風を紹介。「惑星」を思わせる低弦の神秘的な響きから始まり、弦のメロディに金管の不規則な持続音がからんだり、木琴や太鼓が活躍したりした後いったん静かになるが、最後に超新星のような大爆発。カーテンコールでステージに上がった作曲者はよほど演奏が気に入ったのか、クラリネットなどのソリストを立たせていた。
グラズノフは20分ほどの短い曲。昔N響定期で藤川真弓さんが弾いたのが印象が残っているが、意外と取り上げられていないように思う。スナイダーはデンマーク出身、97年のエリーザベト王妃国際コンクール第1位。ロストロさんの頭が肩にも届かないほどの大男。
しかし、演奏ぶりは至って繊細。冒頭の悩ましいメロディをppで優しく弾き始め、後半のカデンツァまでは傷ついた彼女をいたわるような弾きぶり。最後のイ長調の部分でやっと伸び伸びした音が出てくる。やっぱりいい曲だよなあ。
カーテンコールではロストロさんと肩を組み合ってしゃがんで見せるなど、愛嬌のあるところも見せる。
さて、後半はロストロさん得意中の得意の「タコ5」。指揮棒を持たずに登場(ゲルギエフの影響か?)。第1楽章冒頭こそ堂々とした響きだが、練習番号1(音楽の友社出版のスコアによる、以下同様)からの第1ヴァイオリンのメロディでは時間が止まったみたい。6から4小節目、ホルンが文字通りフォルテで入るあたりからテンポが速くなり、途中で間を取らずにどんどん進んでいく。17から入るピアノ、続いて入るホルンも普通より大きめ。こっちのレストランで大皿に山盛り入ったサラダやステーキがどかっどかっと出てくる感じ。さらに突進していき、27の行進曲風のところに入ってもテンポが落ちない。さすがに36手前で少し遅くなるが、36のユニゾンになるとまた速くなる。39弦のタンタタでようやく落ち着く。フルート・ソロ(河野俊子さん)が、廃墟をさまよううちやっと見つけた一輪の花のように美しく、思わずホロリときた。世の中、悪いことばかりじゃないんだ…
第2楽章、弦も管も徹底したレガートで演奏させるのにびっくり。1小節目2泊目の休符なんて無視。そして、54の「A−H−C」でぐっとテンポを落としてアクセントを強調。他方トリオでは58のヴァイオリンのグリッサンドで最高音を大げさな投げキッスのように強調するなど、色気たっぷり。農夫とジプシーといった感じ。
第3楽章、やはりやや遅めのテンポで始まるが、78で第1ヴァイオリンが力強く入るところからスピード・アップ。その後少し落ち着くところはあるが、全体的には速いテンポ。89の1小節前から始まるクライマックスでもテンポは落ちず、90のチェロのパート・ソロに入る前も間を入れない。92の最初2小節をたっぷりレガートで弾かせてからやっと落ち着き、96のハープとチェレスタのメロディでさらに遅くなる。
間髪入れず第4楽章へ。またも遅めのテンポで始まるがだんだん速くなり、106でトランペットが入るあたりから超特急に。111の銅鑼が入ったところでやっと落ち着く。その後は逆に最後まで遅いテンポを貫く。金管はかなりきつそう。他方弦にはレガートを徹底、ホールを音で埋め尽くす。最後の音を振り終わったところで団員に向かって「どや!」と言わんばかりに胸を張る。
聴衆の多くがスタンディング・オベーションを行う中、ロストロさんはステージの奥まで入っていき、管の首席を立たせたり、パートごとに立たせたりしてねぎらう。チェロの最前列の奏者たちとは抱き合いキスまでし合っていた。かつてはこんな光景が当たり前だったのだろう。唯一この恩恵にあずからなかったのは演奏中出入りを繰り返したチェレスタ奏者のみ。
泥臭いが人情味で聴衆を惹きつけた前音楽監督。熱くはないが知的アプローチで聴衆をリードする現音楽監督。フルシチョフとケネディに喩えたら的外れだろうか?いずれにせよ、2人ともDCの聴衆にとってかけがえのない「フレンズ」であることは間違いない。
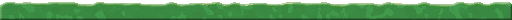
表紙に戻る
