 ワシントン・ナショナル交響楽団定期演奏会(3回公演の2日目)
ワシントン・ナショナル交響楽団定期演奏会(3回公演の2日目)
○S=ドミニク・ラベル、MS=ジル・グローヴ、T=エリック・カトラー、B=エリック・オーエンス、レナード・スラトキン指揮ワシントン・ナショナル交響楽団、ザ・コーラル・アーツ・ソサエティ・オヴ・ワシントン(女声約100人、男声約80人、合唱指揮:ノーマン・スクリブナー)
○2月13日(金) 20:00〜22:10
○ケネディ・センター・コンサート・ホール(米国ワシントンDC)
○Second Tier F-30(4階席最後列上手端)
○ベートーヴェン「交響曲第9番ニ短調作品125」(合唱付)(マーラー校訂)
(15-15-11-12-8、対抗配置)(約75分)(第2楽章前半とトリオ前半のみ繰り返し実施)

サルでもわかる「第9」?
先週の定期が評判を呼んだのか、あるいはやはり「第9」のブランド力なのか、今週の定期もほぼ完売。どうしても初日に行けず2日目のチケットを買ったら、最上階の上手側どん詰まりの席になってしまった。今朝のワシントン・ポスト批評の見出しは「あまり喜ばしくない(less-than-joyful)第9」とあったが、本文は読まずに会場へ。
ステージには奏者がぎっしり。合唱用のヤマ台があるだけでなく、前回同様管楽器が大幅に増員されているからだ。フルート4、それとは別にピッコロ2、オーボエ・クラリネット・ファゴットは各4、ホルンが何と9人!トランペット4、トロンボーン3にチューバ。うん?「第9」にチューバなんてあったっけ?
前半は先週同様スラトキンによる演奏付解説が約30分。今回も特徴的な点を挙げてみる。
1.フレーズの句読点を明確に
例えば第4楽章、チェロ、コントラバスによる8〜16小節のメロディを1拍半か2拍くらいずつ区切って弾かせ、最後は消え入るようなディミニエンドをかける
2.ベートーヴェン時代の楽器では演奏できなかった部分などの補強
例えば第4楽章冒頭、トランペット、トロンボーン、チューバに木管と同じフレーズを吹かせる
3.強弱の強調
例えば第1楽章301小節以降ティンパニの連打で波のようなデクレッシェンドとクレッシェンドを繰り返す
4.隠れがちなフレーズの明確化
例えば第3楽章133〜136小節の第2ヴァイオリンの「タタター」をしっかり聞かせる
今回さすがにポルタメントはなし。第1,4楽章でオーボエとクラリネットをベルトップで吹かせる場面があったが、ホルンはなし。マーラー自身が作曲した交響曲にはしばしば登場するが、彼にしてみればfの数を増やす程度の感覚でやらせていることがわかる。
こうして見ると、現代の指揮者の多くが当たり前のようにやっていることも多い。そういう所は「校訂」と言うより「解釈」と言った方が適切かも。
傑作だったのは、第2楽章93〜108小節の部分(330〜345小節も同様)。何でもスラトキンが学生時代に聴いた指揮者がまちまちな演奏をするので、いったいこの曲にはいくつ版があるのか、友人たちと大論争になったそうである。そこでマーラー校訂だけでなく、ワーグナー、R.シュトラウス、トスカニーニ、バーンスタインの例まで演奏して聴かせてくれる。トスカニーニが原典通りにやるのはわかるとして、ワーグナーとR.シュトラウスは木管のメロディにホルンを追加、バーンスタインとマーラーはさらにトランペットを追加しているのである。
休憩後合唱団もヤマ台と「コリスター」と呼ばれるステージ後方の席に着席。なぜかコリスターのメゾパートの最前列が空いていて、一部団員がステージ下手側の席にいる。変だなあと思っていたら第2楽章の後ソリスト4人が空席の端、すなわち舞台中央に座り、その続きに残りの団員が移動。なるほど。それにしても楽譜を持って歌う「第9」は久しぶりかも。
さて全曲やるとどうなるのか?スラトキンがマーラー校訂の箇所をできるだけ忠実に聴かせようとするせいか、全体的にスロー・テンポ。上記以外にも耳慣れない響きがたくさんあるのだが、パラパラ漫画を1枚ずつめくって見るか、パワーポイントのプレゼンを見ているような気分。
第4楽章でバスが歌い始めるとそれにからむオケ、特に木管がよく聴こえる。終盤865〜868小節ではフルート、ピッコロ、クラリネット総勢10人のトリルで盛り上げる。オケは終始マーラー風だが、ソリストと合唱はごく普通に歌っている。マーラーは合唱部分までは手を加えなかったのか、それともスラトキンの指示が浸透していないのか?どうにも声の存在感が物足りない。
演奏が終わると聴衆は総立ちに。しかし、いつものように舞台袖から2回呼び出されると拍手は止み、早々と聴衆は帰り始める。ロビーには合唱団のメンバーが着替えもせずに出てきて、聴衆と一緒に駐車場へ向う。車社会ゆえの奇妙な光景だが、僕も含め聴衆は皆「第9」が完璧にわかったつもりになったことだけは間違いない。
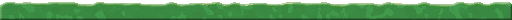
表紙に戻る